発達障害には、色々な診断名(自閉症スペクトラム障害、ADHDなど)併存障害(チック、強迫性障害などがあります。
しかし、これらの診断名はDSM-5 ICD-10およびICD-11の診断基準(こどもにみられる症状がいくつ当てはまるか)によって決定します。
それには客観的な指標(血液検査、脳スキャン)はなく、医師の主観です。
そのため、医師の違いにより診断名が変ってしまうことも少なくありません。
このように症状だけで判断し、客観的な指標がない発達障害を先天的な脳機能障害としてしまうことには疑問が残ります。
有効な西洋医学的な治療方法がない=先天性ではありません。
カイロプラクティック心は、発達障害の診断名に左右されることなくfunctional disconnection syndrome(FDS)として評価、アプローチを行います。
また、カイロプラクテイック心は発達障害に有効なBBIT認定療法士でもあります。
FDSは以前からある概念ですが、脳科学の研究が進歩するにつれて発達障害の脳の状態を研究する文献も多数発表され、発達障害を説明する基礎となります。
ここでは、FDSについて詳しく解説していきます。
発達障害についてはこちら
functional disconnection syndrome(FDS)
functional disconnection syndromeを直訳すると機能的分離症候群となります。
機能的分離とは、外科的切除、外傷、病変による大脳半球の物理的な切断ではなく、解剖学的に損傷がない場合の脳の機能異常です。
左右の大脳半球の機能的な偏りによって、様々な症状が現れます。
このコンセプトは1972年にリースマンによって作られ、以下のように研究が勧められました。
現在の機能的切断の概念は、自閉症スペクトラム障害の性質の理解に適用され発展し、ケンブリッジ大学の自閉症グループは、内側側頭葉構造の機能的結合性がアスペルガー症候群の人で特異的であることの証拠を提供しました。
メリロとリースマンは同様に、機能的切断症候群が自閉症スペクトラム障害の症状を説明するための基礎であると結論付けています。
引用元:ウィキペディア
FDSの概念をもとに発達障害へのアプローチ法が書籍になっています。
日本語訳では「薬に頼らず家庭で治せる発達障害との付き合い方」
日本語訳の著者である吉澤D.Cは、日本でBBITを設立して療法士の育成もされており、カイロプラクテイック心はBBITの認定療法士の資格を取得しています。
BBITについてはこちらの記事でも解説しています。
脳の発育
脳は下部(脳幹)から上部(大脳皮質)へ向かって発育し、左右の脳半球が交互に成長していきます。
もう少し具体的に説明すると、出産後の乳児は脳幹部の反射(原始反射)に頼っておっぱいを飲む、しがみつく、危険を感じたら泣く、寝返りをするというような行動ができます。
そして、光、匂い、音、温度、味、重力など刺激を受けることで脳が発育し、それに伴い情報処理のスピード高まり、意思、行動を現すようになります。
2~3歳くらいまでは右脳が優位に発育し、その後左脳が発育して2~3年のスパンで交互に成長し20歳くらいで脳が成熟するとされています。
右脳が先に発達する理由としては、脳の局在性が関係しているからです。
左脳は言語、算数、論理的思考などに優位性があり、反対に右脳は感情や共感性、相手の感情を読むなどの優位性があります。
そのため、話すことができない、論理的思考が未熟である乳幼児は、母親を含めた家族、友人などの表情や言葉の抑揚などを読み取る右脳が優先的に働いています。
そして、言語の発達していない乳幼児は、表情や身振りなどで親に理解を求めます。
1歳過ぎから簡単な言葉を発しながら、左脳も働き始めます。
例えば、1~2歳の頃は言葉で表現できないため、叩いたり、泣いたりして嫌なことを拒みます。
言語学習がある程度行われた3歳以降になると言葉で伝えることも多くなり、表情と言語も一致するようになります。
脳の発育過程で刺激が不足、偏った刺激、左右どちらかが優位に成長したなどによって、脳の偏りがみられると考えられます。
後天的なリスク
なぜ、乳児から受け取るべき刺激が不足したり、偏った刺激になってしまうのでしょうか。
現代社会は、便利になった反面、こどもの成長を促す刺激が不足しがちです。
スマホ育児、座らせて遊ばせるおもちゃ、チャイルドシートに乗せて長距離移動など利便性は格段に向上しましたが、運動から得られる刺激を受けられないことが多くなりました。
幼児期でも寝返り、ハイハイ、指吸などは原始反射を統合していく上で、身体を動かすことは重要です。
また、外で遊べるようになる時期に筋肉や関節だけではなく、目に見えるもの、聞こえてくる音、匂い、土の味などの5感と呼ばれるものにまで刺激が入ります。
これらの刺激が脳に伝わることで、情報処理能力が発達し、入ってきた刺激に対して表現するようになるため、脳がどんどんと成長していきます。
また、右脳と左脳の発育を考えた場合、右脳の発達が優位な3歳くらいまでのときに、両親から語りかけ、非言語コミュニケーション(表情やしぐさから読み取る)を学べないと右脳の成長が上手くいきません。
それが結果として言語脳とされる左脳も上手く発育せず、言葉の遅れとなることが多いです。
運動の重要性
宇宙飛行士が無重力の世界から帰還した際、学習障害に似た精神障害を引き起こすことがあります。
そのため、宇宙飛行士のリハビリ(前庭神経への刺激)がディスクレシア(読字障害)に有効とも言われています。
このような事例だけでも、重力は脳への刺激になっていることが解ります。
人は重力に対して筋肉をコントロールしながら、バランスをとって(とくに2足歩行)生活しています。
この生活に重要になるのが、筋肉や関節にある固有受容器です。
そのため、立っているだけでも固有受容器が刺激されることになります。
しかし、発達段階で座らせたまま移動、長時間のスマホやテレビ視聴を行えば、十分に固有受容器への刺激が受け取れません。
Hemisphericity Model(ヘミスフェリシティ理論)
繰り返しになりますが、脳の成長には感覚器(重力:固有受容器、視覚、聴覚、内臓感覚など)から十分に刺激を受け取る必要があります。
そして、それらの情報を処理、整理し表現(行動、コミュニケーション、感情、学業など)します。
感覚の受け取り、情報処理、表現のバランスが崩れることで発達障害のような症状がみられます。
また、発達段階のいつから問題が生じたか、脳のどちら側のバランスが崩れたのかなどによって表現の仕方が変り、診断名も変わると考えられます。
このように左右の脳バランスが崩れた機能低下側をヘミスフェリシティとも呼ばれます。
脳の特性
両側の脳に同じ機能(言語、創造性など)はありますが、それぞれ優位に働く特性を脳は持っています。
右脳の特性
- 大きな関節の筋肉をコントロール
- 空間的脳 (空間中の自分の位置感覚)
- 社交性 (人との関わり、人との共感など)
- 無意識脳
- 感覚脳 (感情を感じる、 内臓や身体全体の感覚能力)
- 低周波の音を聞き取る
- 回避脳(いやな匂いや味などの感覚から人や物を回避する判断)
- ネガティブ感情(注意深い、恐怖、悲しみ、憤慨など)
- 注目、集中、衝動の抑制
以上が主な右脳の機能です。
これらが機能しないと以下のような行動、表現がみられます。
- 運動が苦手、姿勢が悪い、歩き方が変(筋肉、関節のコントロールが未熟なため)
- 人との距離感が近い、もしくは遠い(自分の位置感覚が乏しいため)
- 人の感情が読めない
- 不適切な行動、発言
- 突発的な感情爆発
- 衝動的な行動
- 落ち着きがない
このように右脳の機能が低下していると自閉症スペクトラム障害、ADHDでみられる初動的な行動、社交性がない運動が苦手などがみられることがあります。
※右脳の機能低下=ASD、ADHDではありません。
左脳の特性
- 小さい筋肉のコントロール(手先の細かい作業、声帯やしゃべる為の筋肉など)
- 一定のリズムを処理する
- ポジティブイモーション(楽しむ、幸せ、前向き、アクティブ)
- 言葉を読む、書く、理解する
- 意識して行動を起こす、頭の中で考える
- 理論的脳
- 注意力とパターン認識は言語習得に大切
- ルーティーン脳
- 衝動脳
- 考える脳
- 知りたがり脳=興味、言語知性
以上が主な左脳の特性です。
これらが機能していないと以下のような行動、表現がみられます。
- 引っ込み思案 ぐずぐずしてみえる(意識して行動する能力が低下しているため)
- 運動能力は高いがルールが理解できない為、サッカーやバスケットボールなどのチームスポーツは苦手
- ダンスなどは苦手(リズムを処理能力が乏しいため)
- しゃべりだすのが遅く、読む、しゃべるが苦手(注意力とパターン認識が乏しいため)
- 字がとてもきたない(小さい筋肉のコントロールが苦手なため)
- 数字に弱い(パターン認識が苦手)
- 本を読むのが嫌い
- 自分がどのように見られるか気になる
- 人見知り
このよに左脳が機能低下していると学習障害でみられる読み書きの困難がみられるようになります。
また、場面緘黙や聴力・視力が正常であっても処理が苦手であるため、学習に困難をきたす問題もみられます。
言葉で表現することが苦手であり、しゃべりだすことが遅いことからASDと診断されたり、注意力やパターン認識も乏しいため、ADHDと診断される可能性もあります。
FDSの症状
先にあげた症状以外にも以下のような症状が多くみられます。
乏しい身体感覚
空間で自分がどのような姿勢、動きをしているかを脳に伝える固有受容器、前庭神経系が育っていないため、姿勢が悪かったり、動きにぎこちなさがみられます。
他にも背中に自分の手を回すと自分の手を感じることができない、バランスが悪い、鏡にうつる自分の部位も識別できない(目を指すように指示しても鼻を指すなど)がみられます。
自分の身体でさえも認識できないため、感情も不安定となり社交性の問題にもつながります。
原始反射の残存
本来なら1~3歳の間には統合される原始反射が、残存しています。
原始反射は、発達の基礎となるため、それらが残っているということは発達でのつまづきがみられることを示唆します。
大人でも原始反射の残存がみられることもありますが、脳が未成熟なこどもは生活の中で反射の影響をとても受けやすくなります。
例)
- モロー反射⇒大きな音やびっくりする出来事に過剰な反応を示す
- TNR⇒姿勢が悪い、バランス感覚ない、人との距離感がつかめない
- ガラント⇒おねしょがなおらない、じっと座れない
- 探索・吸啜反射⇒言葉や発音の問題
- 把握反射⇒手先が不器用、書字の問題
- バビンスキー反射⇒歩き方が変、バランスが悪い
- ATNR⇒目と手の協調性が悪い、目の動きが未熟で文章を読むことが苦手
- STNR⇒遠近感をつかめない
原始反射について詳しくはこちら
眼球コントロールが乏しい
あるものをジッとみていられない(注視が出来ない)、ものを目で追うことができない、寄り目が出来ない(遠近の距離感がつかめない)など、眼球の動きに問題がみられます。
遠近を目で調整できないため、身体を動かして調整することで落ち着きがなく見えたり、目で追えないため本を読むことが苦手になったりします。
これだけではなく、目のコントロールが乏しいことが社交の問題、運動の苦手、不注意など様々な問題にむすびつきます。
「視覚優位」と呼ばれるケースでも、他の機能が低下しており、視覚を使わざる負えない状況であることも少なくありません。
そのため、視覚に頼った生活によって過度なストレスを与えてしまうこともあります。
視覚についてはこちらもご参考ください。
乏しい社交スキル
3歳くらいまでは右脳が優位に成長します。
この時期に非言語コミュニケーション(顔の表情、声のトーンなど言語以外で察する能力)が発達するとされています。そして、非言語的コミュニケーションが言語コミュニケーションの基礎になっています。
言葉が遅れていることで、言葉を教えようとしても非言語コミュニケーションが発達していないと言葉も理解できず、結果として社交スキルにまで影響を及ぼします。
感情表現の未熟
人にはミラーニューロンと呼ばれるものがあります。
ミラーニューロンは、人の行動を真似するときに活動し、行為の意図まで処理していることが示唆されています。(自閉症スペクトラム障害はミラーニューロンの機能不全も一因とされています)
生まれたときからこどもは、両親の笑顔、喜び、悲しみなど顔の表情などをみてボディランゲージと感情を学んでいます。
非言語コミュニケーションが未発達となるため、適切な行動がとれず(楽しいときに笑えない、喜怒哀楽に表情が伴わないなど)感情と行動がかけ離れてしまいます。
感覚に敏感もしくは鈍感
光や音に過敏であることが多く、なんでもない外の光や普通の音でも我慢できないことがあります。
他にも味や匂いに過敏過ぎて好き嫌いが多くなったり、触覚が過敏で触られるのを嫌がったりすることもあります。
また、これらの感覚を上手く処理できないため、低い音や高い音が聞き取れない、同時に光や音の刺激を処理できないことがあります。
これらとは反対に触覚や痛みの鈍感であることもあります。
たとえば、転んだり頭を打ったりしてもリアクションをみせない、過剰にまとわりつくような行動がみられます。
免疫システムの問題および消化器官の未発達
アレルギー、食物過敏症など免疫システムが過剰に反応していることが多いです。
また、風邪、中耳炎などによくかかることで、聴覚および嗅覚の刺激が不足してしまうケースがあります。
これは免疫系に関与する消化器官(免疫システムの抗体の60%が腸壁に存在すると言われています)が未発達であることが一因でもあります。
アメリカの小児科アカデミーは消化器官の問題で発生するリッキーガット症候群が自閉症の要素になっているとしています。
FDSは回復する可能性がある
FDSは脳が欠損しているわけではなく、神経を繋ぐ接続部が強化(シナプス)されていないため、脳の機能が低下している状態です。
機能低下は、脳のシナプスを強化する刺激を加えていくことで回復が可能です。(脳の可塑性)
脳の可塑性
脳の可塑性は個体の成長、学習・記憶、神経の再生など多くの現象にかかわることが知られている。たとえば、脳の神経が損傷を受けた場合でも、栄養補給・形態修復などでその機能が回復することがある。
また、生後早い時期の神経細胞同士の結合は可塑的であり、その前後でネットワークが大きく変化することがわかっている。
たとえば、ネコに縦じまだけを見せ横じまがない世界で飼育すると、横じまが見えないネコに成長することが知られている。
これは神経系が自己組織的に構造を変化させる柔軟さに起因していると考えられている。
また、神経細胞同士の接合点であるシナプスにあるパターンの電気インパルス (短時間の高頻度刺激) を与えると、シナプス伝導効率が変化し、さらに、このシナプスの伝導効率がしばらくの間保持される現象が起こる。
引用元:ブリタニカ国際大百科事典
ネコに縦じまだけをみせて飼育すると横じまが見えないネコに成長してしまうように、必要な刺激が不足すると脳の特性がバランスよく発達しません。
しかし、不足している刺激を入れていくことで、神経細胞同士の接合点であるシナプスに電気信号が流れ、神経伝達効率が強化され脳の機能を回復させることができます。
年齢を問わず脳の可塑性はおこりますが、とくにこどもは日々脳の可塑性によって脳を成熟させている段階のため、効果的に機能を回復させることができます。
脳の可塑性について詳しくはこちら
脳バランスを評価・改善
ここまで書いてきたようにカイロプラクティック心の発達障害の対応を簡単に説明すると以下のとおりです。
質問票(両親・こども)、成長過程のチェック(ハイハイの時期、しゃべり始めなど)神経機能検査(60種類程度)で脳の左右の偏りを評価します。
そして、左右だけではなく、どの部分がとくに低下しているか(脳幹、小脳、大脳など)までチェックし、低下している部位を中心にアプローチして脳のバランスを改善していきます。
アプローチ方法は、カイロプラクティック施術(固有受容器への刺激、関節の位置覚の正常化に有効)運動療法(神経系の再教育:脳の可塑性)を中心に行います。
BBIT(ブレインバランスインテグレーション)
カイロプラクティック心は「薬に頼らず家庭で治せる発達障害との付き合い方」の日本語の翻訳者である吉澤DCのBBITセミナーを受講しています。
BBITのもとのなる機能神経学は伊藤DCのセミナーを中心に300時間以上履修し、仙台で発達障害への対応している落合カイロプラクティック:吉田先生の指導も受けています。
脳の機能障害が原因とされる発達障害においては、脳の評価および脳の可塑性を促進させるアプローチが大切になり、BBITは発達障害に有効なアプローチ方法です。
主な評価方法
- 原始反射(モロー反射、緊張性前庭迷路反射、探索吸啜反射など)
- 脳神経(嗅神経・内耳神経・視神経・動眼神経・舌下神経など)
- 大脳小脳(指鼻テスト・回内回外テストなど)
- 脊髄小脳(フクダテスト・ロンベルグ・片足バランス【閉眼・開眼】など)
- 前庭小脳(回転後眼振・前庭動眼反射・サッケードなど)
- 体幹テスト(腹筋・背筋、腕立て)
- 利き手・利き足・利き耳・利き目
- 前頭運動野(ペグボード・粗大運動)
- 前眼球眼野(サッケード・眼球追従運動)
- 背外側前頭野(数字順読み、逆読み)
- 前眼窩前頭野(匂いなど)
脳機能のテストは、機器を使用しなくても評価できます。
ただ、年齢によってはできない検査もあるため、できる検査を総合的に見て脳のバランスを評価します。
アプローチ方法
評価方法でできなかった動作がアプローチ方法になります。
ただ、単純な動作なため、こどもが楽しくできるように遊びのように出来るよう工夫することも大切です。(親御さんと相談しながら創意工夫させてアドバイスさせていただきます)
さらには空間的荷重という考えにより、複数の刺激を入れることでできなかった動作を促すこともあります。
例えば、姿勢のコントロールが難しいことで落ち着きのなさ、運動の苦手などがみらたとします。
足元から振動する器具に乗り(固有受容器刺激)頭位を動かす(前庭系)手足の運動(体幹の協調性)などを組み合わせることで姿勢のコントロールが効果的にできることもあります。
評価した内容を参考に運動療法、神経系への刺激、カイロプラクティック施術を組み合わせてアプローチします。
運動療法
主な運動療法は以下のとおりです。
- トランポリン⇒前庭神経、小脳など平衡感覚、体幹のコントロール
- 風船を膨らませる⇒呼吸を大きくさせることで脳全体に酸素をいきやすくする
- 原始反射エクササイズ⇒原始反射を抑制
- クロスクロール⇒手と身体の協調運動
運動はバランス感覚・固有受容器などの感覚器に刺激を入れることができます。これらは人が2本足で立つための基礎発達であり、その感覚が弱いがために姿勢が悪かったり、運動が苦手であったりします。
基礎的な発達が出来ていない状態では、感情もコントロールできません。
五感への刺激
匂い、音、眼球運動、触刺激などを行います。
匂いは嗅神経をとおして眼窩前頭前野(情動をコントロールする領域)への刺激となります。
音は一定のリズムは左脳、オーケストラなどリズムに変調があるものは右脳への刺激に有効です。
発達障害においては目の発達が上手くいっていないことがほとんどで、目で物をみるトレーニングや色の刺激を取り入れます。
触刺激はスキンシップとしても大切ですが、「どんな数字を書いたか」「どこを触ったか」を当てるゲームなどをしながら、頭頂葉への刺激を行うことができます。
カイロプラクティックアジャストメント
必要に応じてカイロプラクティックアジャストメントを行うことで、早期の改善が見込めます。
幼児・乳児であれば触っただけに見えるような刺激でも十分です。
腰痛の研究ではありますが、カイロプラクティックアジャストメントにより脳領域に変化がみられたという研究報告があります。
視床、島、および背外側前頭前野(DLPFC)領域のN-アセチルアスパラギン酸(NAA)、ならびに視床、島、および体性感覚皮質(SSC)領域のコリン(Cho)が治療で有意に増加した。視床、前帯状皮質(ACC)、および視床およびSCC領域のCho代謝物とともにSCC領域のNAAで、ベースライン測定と比較して、治療群での治療後に有意な増加がさらに観察されました(p <0.05)。また、視床のGlx(グルタミン酸およびグルタミン)レベルの有意な増加が観察されました(p = 0.03)。
しっかりと評価し、カイロプラクティックを取り入れることで脳への変化も促すことができます。
まとめ
カイロプラクティック心は、発達障害の診断名にとらわれずに脳の機能のバランスが偏った状態(FDS)を評価し、機能低下した部分を中心に神経機能を回復させるアプローチを行います。
そのため、自閉症スペクトラム障害だからこのアプローチ、ADHDだからこのアプローチという手法ではありません。
多様な症状をみせる発達障害において○○だけで改善する(栄養療法、心理療法など)ことはなく、多様な機能をもつ脳を丁寧に評価して、その人にとって適切な方法を選択することが大切です。
色々な療法を試したけど効果がない、今よりさらに良くなるなら試したという人は、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング
栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群
脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告
部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

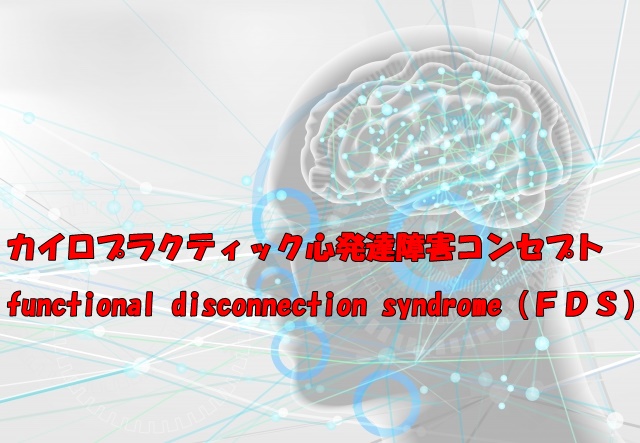






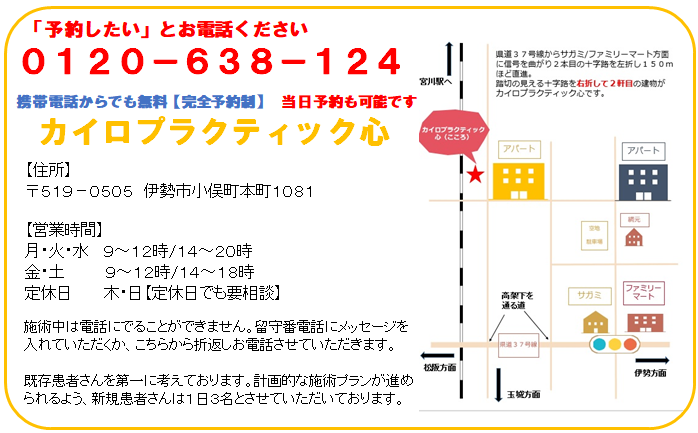






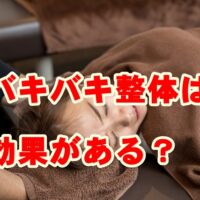













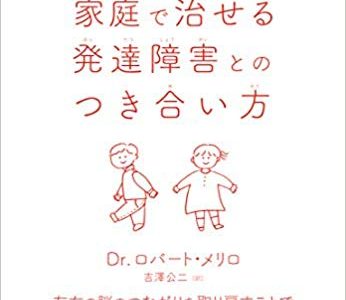


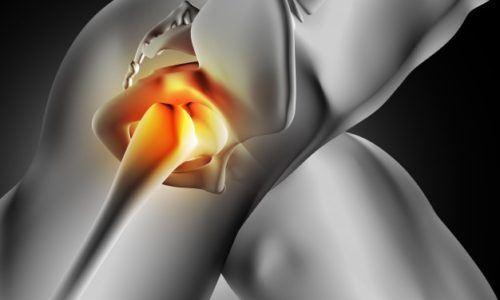


この記事へのコメントはありません。