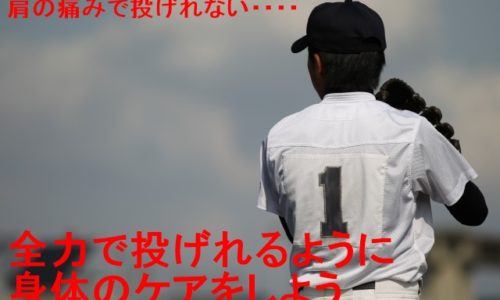-

-

-

-

-

アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ
アトピー性皮膚炎は、増悪と軽快を繰り返す瘙痒のある湿疹を主病変とする疾患です。また、加齢とともに有病率が減少する傾向があります。しかし、一部では成人にな…
-

隠れ貧血?(鉄欠乏)による体調不良(慢性的な疲労感、頭痛など)の対処法
血液検査では貧血と判定されないケースでも、体に鉄が不足している鉄欠乏がみられることがあります。鉄欠乏は、病院では貧血と診断されていないため、原因のわからない…
-

大人のADHDの特徴、支援
最近では、大人になってから発達障害と診断されるケースもあり、ADHD(注意欠陥多動性障害)の特徴によって仕事が上手くいかないことがあります。ADHDは先天的…
-

大人の自閉症スペクトラム障害【女性は気づかれにくい】の対応
自閉症スペクトラム障害(ASD)は、男女の比率が4:1と男性が多くみられることが研究でも報告されています。しかし、女性のなかでも症状がマイルドに現れており、…
-

-

整体・カイロプラクティック人気店の選び方【2024年】
カイロプラクティック?整体?結局どこに行けばええの?と迷われている人へ人口12万弱の伊勢市でも整骨院、整体、カイロプラクティックが増えてきま…