アトピー性皮膚炎は、増悪と軽快を繰り返す瘙痒のある湿疹を主病変とする疾患です。
また、加齢とともに有病率が減少する傾向があります。
しかし、一部では成人になってからアトピー性皮膚炎を発症するケースもあり、大人でも悩んでいることも少なくありません。
このように大人になっても寛解しないようなアトピー性皮膚炎は、ストレスケアおよび栄養が寛解のポイントになる可能性があります。
そのため、病院での治療も大切ですが、なかなか効果が現れない場合は栄養の問題を見直すことが必要かもしれません。
カイロプラクテイック心では、栄養サポートを中心にアトピー性皮膚炎のご相談も承ります。
パッと読みたい人は見出しをクリック
アトピー性皮膚炎の基礎知識
アトピー性皮膚炎は、増悪と軽快を繰り返す瘙痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くは「アトピー素因」を持つとされています。
瘙痒は「搔きたい衝動を引き起こす不快な皮膚の感覚」と定義され、「むずむず」「チクチク」「ジリジリ」など様々な表現がみられることが特徴的です。
頻度は低いですが思春期および成人発症のアトピー性皮膚炎も存在します。
アトピー素因とは?
アトピー素因は、家族歴・既往歴もしくはIgE抗体を産生しやすいといった素因があります。
もう少し詳しく解説すると家族もしくは自分自身に気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患がみられます。
IgE抗体は、免疫グロブリンの一種で、アレルギーの原因物質(アレルゲン)に対して働きかけ、身体を守る機能を持つ抗体であり、アトピー性皮膚炎、喘息、アレルギー性鼻炎では高値を示します。
本来、IgE抗体は血液中に少ないため、アレルギー体質の人に多いと考えられています。
ただ、アトピー性皮膚炎は、アレルギー性鼻炎とは異なり、診断にアレルギーの存在は必須ではないとされています。
病態
様々な病因が複合的に関わる事がアトピー性皮膚炎の病態を形成すると考えられています。
そのため、アトピー性皮膚炎は多病因性の疾患とされ、免疫のバリア機能(主に皮膚)の惰弱性、体質(IgE抗体を産生しやすい)臓器の過敏性などの問題がみられます。
角質の異常
角層は皮膚の表面に存在する厚さ10~20 μmの薄い膜状の構造物であり、体液の漏出防止、角層内水分保持、生体防御(細菌やウイルスなどから身を守る)に貢献する免疫系のバリアを形成しています。
角質は十数層の角質細胞とその間を埋める角質細胞間脂質により構成され、アトピー性皮膚炎では角質細胞間脂質の機能低下により水分の保持能力が損なわれています。
また、バリア機能が低下しているため、アレルギーに対してIgE抗体の産生および炎症が生じやすくなります。
表皮の異常
表皮は、角層を含め基底層、有棘層、顆粒層で構成されています。
そして、角層のバリア構造に加え、その内側に細胞間の隙間を埋めるようなタイトジャンクションと呼ばれる細胞間接着構造のバリアがあります。
アトピー性皮膚炎では、タイトジャンクションのバリア機能の低下もみられます。
炎症
皮膚のバリア機能が低下することによって、アレルゲンが侵入しやすくなります。
そのため、アトピー性皮膚炎では、侵入したアレルゲンに対してIgE抗体を介してサイトカイン、化学伝達物質(ヒスタミンなど)を放出して炎症を誘発します。
さらにヒスタミンは痒み発現させ、皮膚をかくことで皮膚が傷ついたり、病原体が侵入したりすることで炎症はさらに継続します。
原因
アトピー性皮膚炎は、根本的な原因は解明されていませんが、皮膚のバリア機能の低下と免疫系の異常が生じていると考えられています。
その要因として、遺伝的要因や環境要因、心理要因を含む複雑な原因が絡んでいます。
悪化因子としては以下のようなことがあります。
- 温度
- 湿度
- 発汗
- 服の素材(とくにウール素材)
- 精神的ストレス
- 食物(アレルギー食品)
- 風邪症状
- 飲酒
これらの悪化因子がみられれば、管理していく必要があります。
症状の特徴
アトピー性皮膚炎の特徴は以下のとおりです。
- 左右対称性の分布を示す湿疹
- 年齢によって好発部位が違う
好発部位
- 前額
- 眼の周り
- 口の周り
- 口唇
- 耳介周囲
- 頸部
- 四肢関節部
- 体幹
年齢による特徴
乳児期:頭、顔にはじまりしばしば体幹、四肢に下降していく
幼小児期:頸部、四肢関節部の病変
思春期・成人期:上半身(頭、頸、胸、背)に皮疹が強い傾向
病院での診断
アトピーの診断基準(アトピー素因、症状の特徴など)に基づき医師によって診断され、重症度を判断するために質問票や血液検査なども用います。
また、鑑別診断も重要です。
鑑別すべき疾患は、主に以下のとおりです。
- 接触皮膚炎
- 手湿疹(アトピー性皮膚炎以外の手湿疹を除
外するため) - 脂漏性皮膚炎 皮膚リンパ腫単純性痒疹
- 乾癬疥癬
- 免疫不全による疾患汗疹
- 膠原病(SLE,皮膚筋炎)魚鱗癬
- ネザートン症候群皮脂欠乏性湿疹
病院での治療
アトピー性皮膚炎の治療方法は、病態に基づいて以下の3つが基本となります。
- 薬物療法
- 皮膚の生理学的異常に対する外用療法・スキンケア
- 悪化因子の検索と対策
薬物療法は、主にステロイド外用薬が用いられます。
また、ヒスタミンの影響を受けることもあるため、抗ヒスタミン薬が処方されることもあります。
バリア機能の低下している皮膚に対して、外用薬および保湿液などを利用してスキンケアを行い、お風呂の温度やボディーソープやシャンプーなどに過敏性にも注意をはらう必要があります。
悪化因子は人それぞれですが、アレルゲン(食物、ハウスダストなど)発汗、衣服など生活の中で悪化因子があれば、取り除き環境を調整していきます。
アトピー性皮膚炎は大人になっても継続することがある
アトピー性皮膚炎は、年齢とともに寛解していくことが多く、スキンケアや薬物療法で改善されていきます。
しかし、一定数は成人になってもアトピー性皮膚炎が寛解されず悩んでいる人も少なくありません。
その理由はそれぞれあるとは思いますが、一つの要因として栄養の問題が考えられます。
体は栄養素から作られており、皮膚や免疫に必要は細胞なども例外ではありません。
そのため、皮膚を形成する栄養素が不十分であれば、皮膚のバリア機能が回復しないことも考えられます。
また、腸内細菌は免疫系と大きく関わっており、アトピー性皮膚炎を含めたアレルギー疾患との関連を示す研究も多く存在します。
一貫した研究結果が得られていないため、病院の治療として主になっていませんが、腸内細菌を改善させるプロバイオティクスが有効となる人もいます。
なかなか改善がみられないアトピー性皮膚炎に対しては、栄養面から見直していくことが重要と考えられます。
アトピー性皮膚炎と栄養
アレルギー疾患も併発していることの多いアトピー性皮膚炎では、栄養の研究も多くあります。
臨床的にも食事の見直しを実践したクライアントは、アレルギー(花粉症、アレルギー性鼻炎など)でみられる症状が緩和することも多いです。
研究でもビタミンA、D、E、亜鉛、鉄、食物繊維などの栄養素の有効性は示唆されています。
しかし、アトピー性皮膚炎を何とかしたいという想いで良いとされる栄養素を摂取する方もいますが、効果がみられないケースもあります。
その理由の1つとして、食事の基盤ができていないことがあります。
まず食事の見直しで取組むべきは、アレルギーの危険因子を取り除いていくことです。
アレルギー疾患での危険因子は以下のとおりです。
- 食べ過ぎ
- 高たんぱく質食(動物性のタンパク質の摂り過ぎ、ヒスタミンの成分にもなるため)
- 質の低い脂肪の摂り過ぎ(食用油の使い過ぎ、揚げ物の食べ過ぎ、マーガリンやバターの使い過ぎなど)
- 総食物繊維が少ない食事
- 野菜や果物が少ない食事
- お菓子や加工食品の食べ過ぎ
- 亜鉛、鉄、ビタミンA、D、Eの低レベル
アトピー性皮膚炎に限らず、この栄養素が症状を和らげる情報は多くみられますが、まずは全体の食事バランスを見直すことが大事になります。
アトピー性皮膚炎と亜鉛
体内の血清亜鉛濃度を調べた研究では、血清亜鉛濃度が低いとアトピー性皮膚炎の重症度リスクが高まると報告されています。
また、亜鉛補給は、炎症誘発性サイトカイン産生の有意な減少と関連した報告もあり、アトピー性皮膚炎でみられるサイトカインによる炎症の誘発を抑えられる可能性が示唆されています。
参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36483222/
難治性のアトピー性皮膚炎の33名の患者にに対して亜鉛療法を行い30例に効果(痒みの軽減、湿疹の範囲の縮小など)がみられた報告もあります。(参考文献:アトピー性皮膚炎の亜鉛補充療法、医療法人愛星会 星ケ丘皮膚科 有沢祥子)
亜鉛はミネラルの1つあり、成人の体内に2g含まれ、皮膚、肝臓、膵臓、前立腺などの多くの臓器に存在し、さまざまな酵素の構成要素となっています。
また、役割も多岐に渡りDNAの合成、免疫応答の関与、タンパク質の再合成など新しい細胞が作られる組織や器官では必須のミネラルです。
アトピー性皮膚炎と腸内環境
腸内細菌叢と皮膚細菌叢は密接に関連しており、腸内細菌叢の変化が皮膚細菌叢の変化に影響を与えることが示唆されています。
そのため、腸内細菌叢の変化は皮膚疾患に関連していると考えられています(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36900771/
腸内細菌叢の善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌など)を摂取するプロバイオティクスは、複数の研究でアトピー性皮膚炎の症状軽減につながったことが報告されています。(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34335634/)
これらの研究は、一貫した結果は得られていませんが、腸内環境を改善していくことはアトピー性皮膚炎を寛解していくためには重要と考えられます。
ただ、腸内環境を良くするためには、まず悪玉菌の増加を抑える必要があるケースもあります。
また、最近では善玉菌のエサとなるオリゴ糖、食物繊維を摂取するプロバイオティクスも腸内環境を改善させるためには重要と考えられています。
このようなことから、プロバイオティクスだけではなく必要に応じて悪玉菌の増加抑制、プロバイオティクスを取り入れていく必要もあります。
腸内環境は数ヶ月から数年かけて改善していくため、長期的な計画および無理なく継続できることをコツコツ続けていくことが重要です。
カイロプラクテイック心のアトピー性皮膚炎へのアプローチ
アトピー性皮膚炎が病院治療でも改善されない場合は、まず栄養の取り組みが重要です。
また、栄養素をすでに摂取しても効果がみられないケースもありますが、先に解説した通り食事の基本的なバランスが悪かったり、1回の摂取量が多かったりするなど栄養の取り入れ方に問題がみられることもあります。
なかには日々のストレスや交感神経が優位となることで、消化機能が働きづらくなっていることもあります。
このような場合は、カイロプラクティックやエクササイズなどで過剰な緊張を取り除き、消化機能が正常に働きやすくすることが有効となります。
カイロプラクティックアプローチ
- 内臓マニュピレーション
- 頭蓋骨の調整
- 施術
カイロプラクティックのテクニックの1つに内臓マニュピレーションがあり、内臓の機能向上を目的としたアプローチ方法があります。
また、背骨から各内臓にも神経が伸びているため、背骨の問題によって内臓機能に影響を及ぼす考えがあり、背骨へのアプローチは内臓機能を高めることもできます。
1つのチェック方法としてお腹が固く少し押さえただけでも痛みがみられる場合は、カイロプラクティックの内臓へのアプローチが有効となるケースが多いです。
ストレスケア
ストレスが体に悪影響をおよぼす一つの原因は、交感神経を過剰に働かせてしまうことです。
交感神経は、活動するために重要ですが、常に働き続けると体は疲弊し消化機能も働きづらくしてしまいます。
また、交感神経が過剰に働いている人は、副交感神経の活動が低下していることが多いです。
そのため、副交感神経の活動を高めるために迷走神経アプローチ(頭蓋骨療法、迷走神経が通るルートの緊張緩和など)が有効です。
カイロプラクテイック心では、ツールによって自律神経の活動状態を客観的に評価できるため、これらの評価に基づいて迷走神経アプローチを行います。
感覚エクササイズ
体を緊張させたり、交感神経を優位に働かせてしまうのはストレスだけではなく、体をコントロールするうえで重要な感覚の鈍さが起因することもあります。
また、運動は腸内環境を改善させるためにも重要な役割を果たします。
必要に応じて感覚エクササイズを行い、体の緊張を緩和させていきます。
感覚エクササイズについて詳しくはこちら
栄養サポート
現在の食事内容(1週間分を記録)可能であれば血液検査内容を踏まえて、食事の栄養バランス改善のサポートを行います。
より詳細にチェックしたい場合は、ミネラル検査や腸内環境の検査を受けていただき(自己負担)亜鉛補給、腸内環境の改善に取組んでいきます。
カイロプラクテイック心では、高額なサプリメントを販売することはありません。
ご希望に応じて医療機関もお勧めいたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
栄養サポートの料金はこちら
ZOOM相談
オンライン(zoom)、ご来店で相談されたい方は、事前のご予約をお取りください。
相談料として1,000円いただきますが、実際にご予約された場合は、相談料1,000円分を値引いたします。
アトピー性皮膚炎を克服できるようサポート
アトピー性皮膚炎は、まず医療機関にご相談ください。
また、医療機関から切り離すためのアプローチではありませんので、通院しながらでも大丈夫です。
医療機関でも改善がみられない方で、何か良い方法はないかお探しの方は、ぜひご相談ください。
アトピー性皮膚炎を克服して、今まで出来なことがあればチャレンジできるようサポートいたします。
参考文献
アトピー性皮膚炎ガイドライン2021
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害







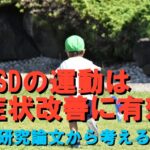











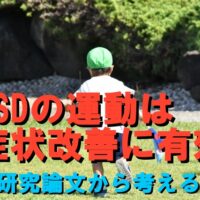





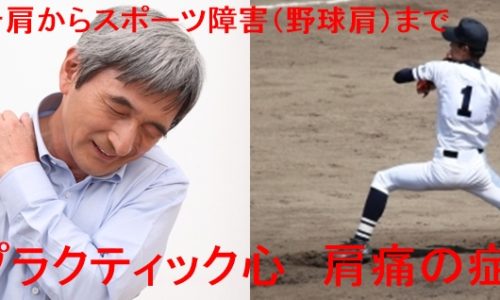




この記事へのコメントはありません。