群発頭痛は、片側の目からこめかみ付近に激しい痛みを訴えます。
また、頭痛を含めた随伴症状は数週間から数ヶ月(群発期)毎日続きます。
国際頭痛分類第3版では、「群発性頭痛および三叉神経・自律神経性頭痛」分類されており、頭痛だけではなく副交感神経系の自律神経症状も伴うことが特徴的です。
ここでは、群発頭痛について原因やセルフケア(対処法)、カイロプラクティック改善方法について詳しく解説していきます。
カイロプラクテイック心の頭痛全般の考え方はこちらもご参考ください
群発頭痛とは
群発頭痛は、目からこめかみ、側頭部にかけて激しい頭痛がある期間中、毎日続くことが特徴です。
また、頭痛発作は、夜中あるいは睡眠中に起こりやすいです。
国際頭痛分類第3版では、繰り返される群発性頭痛は「反復性群発性頭痛」「慢性群発性頭痛」に分類されます。
片頭痛や緊張型頭痛に比べると発症する人が少なく、自律神経症状も伴い、以前は精神疾患として扱われてしまうこともあったそうです。
また、20~40代の男性に多くみられます。(以前に比べ女性と男性の差が減っているそうです)
症状
目の周囲、こめかみ、側頭部、前頭部をえぐられるような激しい頭痛が、15分~3時間続きます。
この頭痛発作は、ほとんど夜中、もしくは就寝中に起こり、数週間から数ヶ月の間、毎日続きます。
また、随伴症状として目の充血、眼瞼下垂(瞼が下がる)、顔面の発汗、涙と鼻水が出るなどの自律神経症状がみられます。
しかし、群発期以外では頭痛が起こることはありません。
診断
国際頭痛分類に基づいて診断が行われます。
A.B~Dをみたす発作が 5回以上ある
B.未治療の場合、重度~きわめて重度の一側の痛みが眼窩部、眼窩上部または側頭部のいずれか1つ以上の部位に、15~180分間持続する
C.以下の1項目以上を認める
1.頭痛と同側に少なくとも以下の症状あるいは徴候の1項目を伴う
- 結膜充血または流涙(あるいはその両方)
- 鼻閉または鼻漏(あるいはその両方)
- 眼瞼浮腫
- 前額部および顔面の発汗
- 前額部および顔面の紅潮
- 耳閉感
- 縮瞳または眼瞼下垂(あるいはその両方)
2.落ち着きのない、あるいは興奮した様子
D.発作時期の半分以上においては、発作頻度は 1回/ 2日~ 8回/ 1日である
E.ほかに最適な ICHD-3 の診断がない
反復性群発頭痛
A.群発性頭痛の診断基準を満たす発作があり、群発期が認められる
B.未治療の場合に7日~1年間続く群発期が、1ヶ月以上の寛解期をはさんで2回以上ある
※群発期は通常2週~3ヶ月続く
慢性群発頭痛
A.群発性頭痛の診断基準を満たす発作があり、Bを満たす
B.1年以上の発作が起きており、寛解期がないか、または寛解期があっても1ヶ月未満である
その他
国際頭痛分類第3版では、「群発頭痛および三叉神経・自律神経頭痛」に分類され、群発頭痛とよく似た症状が現れる頭痛は以下のとおりです。
- 発作性片側頭痛
- 短時間持続性発作性片側神経痛様頭痛発作
- 持続性片側頭痛
- 三叉神経・自律神経性頭痛の疑い
片側頭痛と群発頭痛の症状はよく似ていますが、片側頭痛はインドメタシンの経口投与がとても有効であり、診断基準の1つになります。
神経痛様頭痛発作は、三叉神経支配領域の痛み(顔を含めた頭部が三叉神経支配領域)や短時間の発作を数十回繰り返すことが特徴となります。
疑いとなるケースは、診断基準のうち1項目のみ満たさないケースです。
一般的な群発頭痛治療(病院)
群発頭痛の治療には、急性治療と予防治療があります。
急性治療は頭痛発作時の治療となり、予防治療は発作(反復性、慢性)を予防する治療となります。
ただ、予防治療においては効果的な方法が少ないです。
スマトリプタン
スマトリプタンの皮下投与は副作用が少なく、群発頭痛の軽減に有効とされています。
群発頭痛の発作時に病院へ向かうことは時間的にも難しいですが、自己注射する方法があります。
ただ、注射の手段に抵抗がある人も多く、この方法は普及していないそうです。
代わりに保険適応外ですが、スマトリプタンの点鼻薬が一般的に使用されることが多いです。
純酸素吸入
純酸素の吸入は有効という研究報告があり、日本でも平成30年度から保険が適応されるようになりました。
しかし、今までの治療で効果がみられる人においては、保険適応外となります。
リドカイン
リドカイン(表面麻酔薬)をスプレーで、鼻の粘膜につけます。
手軽できますが、保険適用されておらず、さらにはスマトリプタン、純酸素吸入ほどの効果は認められていません。
急性治療には、エルゴタミン、鎮痛薬も使用されますが、有効性はスマトリプタン、純酸素吸入には劣るとされています。
予防治療
60例の群発頭痛患者をフォローした調査では、26.5%が1回の群発頭痛で済んでおり、83%は2回目の群発頭痛を3年以内に経験していると報告しています。
群発期が2回以上ある群発頭痛において予防治療が行われますが、研究で効果が認められている治療法は少ないです。
日本で認められているものな治療法は以下のとおりです。
- カルシウム拮抗薬(ベラバミル)
- 副腎皮質ステロイド
- 短酸リチウム
- 神経ブロック
群発頭痛の予防は?
群発頭痛は激しい痛みですが、症状は長くても3時間程度で終わります。
また、夜中に発作が起こることが多く、専門医を受診する頃には症状が治まっています。
初めての群発性の頭痛を経験した場合は、群発頭痛を疑って専門医に相談しましょう。
群発頭痛を1度経験するだけで済めば問題ありませんが、数回経験する反復性群発頭痛、慢性群発頭痛もあるため、予防していくことも必要ではないでしょうか。
予防治療は医学的には確立されていませんが、危険因子や考えられている原因に対処していくことが群発頭痛の予防になります。
そのため、群発頭痛を経験した人は予防の意識が大切になります。
群発頭痛の原因
群発頭痛のはっきりとした原因はわかっていないことが現状です。
しかし、頭痛発作時を研究した報告では視床下部、三叉神経の問題が示唆されています。
視床下部の問題
視床下部の問題においては、サーガディアンリズムに関係しているメラトニンの変化が群発頭痛患者にみられるため、サーガディアンリズムに関与する視床下部が疑われます。(視床下部は自律神経の中枢です)
PETを用いた画像診断では、頭痛発作時に後部の視床下部が活性化していることが証明されています。
※PETとは、Positron Emission Tomographyの略で日本語では陽電子放射断層撮影
三叉神経血管の問題
三叉神経活性化の指標となる外頸静脈血カルシトニン遺伝子関連ペプチドが群発頭痛発作時に増加し、スマトリプタン皮下注射で低下していることがわかりました。
そのため、群発頭痛では三叉神経血管系が活性化していると言えます。
内頸動脈の問題
内頸動脈という頸部の動脈は、頭部(目、大脳、中脳など)の血管に分岐します。
そのため、何らかの原因で血管拡張が生じることで群発頭痛が発生すると考えられています。
また、内頸動脈は自律神経との関りがあり(内頸動脈にある受容器が自律神経を介して血圧の調整を行います)、鼻水や涙などの自律神経症状が現れます。
三叉神経の過剰興奮による副交感神経の活性化
三叉神経の活動が高まることで副交感神経が興奮し、鼻水や流涙、ホルネル徴候、結膜充血などの症状が現れると考えられています。
誘発因子
群発頭痛は定期的に発生しますが、誘発されやすい以下の原因があります。
- ニトログリセリン(血管拡張薬)
- ヒスタミン
- アルコール飲料
ヒスタミンは体内で生成され、群発頭痛で関与が考えられる視床下部、血管拡張、サーガディアンリズムに作用します。
ヒスタミンは気圧が下がっているときに多く分泌されるため、気圧の変化の大きい季節の変わり目に発作が起きやすいです。
増悪因子
群発頭痛患者に多くみられる生活習慣は「大酒家」「ヘビースモーカー」です。
アルコールは、群発頭痛の誘発因子でもあり、お酒を飲んだことをきっかけに群発頭痛の発作が続くことがあります。
群発頭痛のセルフケア
群発頭痛のセルフケアは、誘発因子、増悪因子による発作の発症を防ぐことが目的です。
お酒とタバコを控える
群発頭痛を発症した人にとっては、お酒、タバコはリスクであり控えたほうが良いでしょう。
群発頭痛は、激しい痛みが定期的に続くため、日常生活に支障をきたすレベルは、片頭痛患者と同程度またはそれ以上という研究報告があります。
また、経済的損失を調査した研究では、6ヶ月の観察期間中、65,963円の損失という報告があります。
快適かつ経済的損失を防ぐためにも群発頭痛を経験した人は、お酒やタバコを止めることを検討してください。
気圧の変化に注意する
気圧の変化は天気だけではなく、飛行機、トンネルの中、登山などでも生じます。
そのため、群発期間中はこのような環境の変化がみられる場所は避けたほうが良いです。
どうしても行かなければいけない場合は、医師に相談してください。
カイロプラクティック心の群発頭痛アプローチ
群発頭痛は、中枢神経系(脳)の原因が示唆されています。
また、群発頭痛は片側に発症するため、脳の左右のアンバランスも原因の1つとカイロプラクティック心では考えています。
カイロプラクティック心では、機能神経学的に身体評価を行い、脳のアンバランスも評価していきます。
中枢神経(脳)末梢神経(脳以外の筋肉や関節などをコントロールする神経)は相互作用があり、どちらも正常に働いている必要があります。
脳と身体(関節や筋肉など)の問題をみつけ、それを改善していくことで群発頭痛に対処していきます。
施術
- 機能神経検査
- 頭蓋骨の調整
- 施術
- ホームケア指導
中枢神経系の問題⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント、眼球運動、バランスエクササイズなど
末梢神経系の問題⇒筋伸長テクニック、カイロプラクティックアジャストメントなど
ホームケア指導⇒栄養、簡単なエクササイズ
カイロプラクティック心は施術歴15年の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。
また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。
頸椎の調整
群発性頭痛に起因している三叉神経は、頸椎1~3番までにある頸神経とともに収束しています。
そのため、頸椎のカイロプラクティック施術によって、群発性頭痛の予防、軽減が期待できます。
比較的、頻度の高い片頭痛も三叉神経との関与も示唆されており、頸椎の施術によって改善されることがあります。
また、頸椎の調整によって間接的に、血圧の調整に関わる小脳へ刺激となることも有効である可能性もあります。
※評価によって小脳の機能低下が考えられる場合
自律神経アプローチ
視床下部の問題や気圧の変化が起因していることが考えられており、自律神経系へのアプローチも有効と考えられます。
自律神経系へのアプローチはこちらもご参考ください。
栄養サポート
アルコールの過剰摂取は、ビタミンB群の不足を招く恐れがあります。
ビタミンB群は、サーガディアンリズムに必要なメラトニン、セロトニン、ドーパミンなどの神経伝達物質に必要な栄養素です。
また、群発性頭痛ではありませんが、頭痛は栄養不良が関わっていることも多くみられます。
そのため、栄養サポートも重要であるケースも少なくありません。
群発頭痛を予防して快適な生活を
群発頭痛は、日常生活にも支障をきたすほどの痛みです。
そのため、群発頭痛を発症したら生活習慣を見直し、予防していくことが大切です。
また、今までの生活習慣、仕事環境、過去のケガなどによって脳のアンバランスが生じていることも少なくありません。
脳は自律神経や三叉神経をコントロールしているため、脳のアンバランスが群発頭痛に引き金になっている可能性もあります。
「群発頭痛を予防したい」「群発頭痛の発作を早く改善したい」「快適な生活を送りたい」という人は、ぜひカイロプラクティック心にご相談ください。
一緒に群発頭痛を解消していきましょう。
参考文献
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害








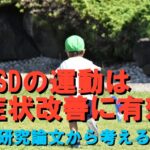






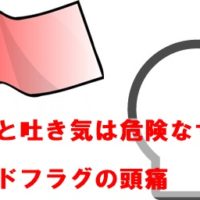




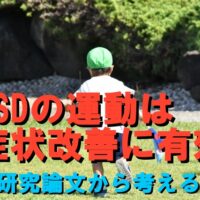










この記事へのコメントはありません。