頭痛のなかには、毎日のように続く慢性頭痛があります。
慢性頭痛は、いくつかに分類されますが、それらを包括して慢性連日性頭痛と呼ばれます。
一般的な有病率は約3~4%、12~14歳でも約1.5%と報告され、日常生活にも支障をきたす頭痛です。
当然、危険な頭痛、病院での治療が有効な頭痛を鑑別する必要はあるため、病院を受診することが大切になります。
ただ、毎日続く頭痛のなかには治療法が確立されていないため、なかなか改善されないケースも少なくありません。
病院で解決できない場合は、頸性や神経機能の低下がみられるケースがあり、これらの頭痛はカイロプラクテイック心でも対応可能です。
ここでは、毎日頭痛が続く慢性連日性頭痛についての原因や対処法を解説します。
カイロプラクテイック心の頭痛全般の考え方はこちらもご参考ください
パッと読みたい人は見出しをクリック
慢性連日性頭痛とは
慢性連日性頭痛は、1日に4時間以上の頭痛が15日以上が少なくとも3ヶ月続く頭痛を指し、以下の4つの頭痛に分類されます。
- 変容性片頭痛
- 慢性緊張型頭痛
- 新規発症持続性連日性頭痛
- 持続性片頭痛
ただ、現在の国際頭痛分類第2版では、慢性連日性頭痛の病名は採用されておらず、変容性片頭痛も慢性片頭痛に分類されるようになりました。
これらの頭痛との鑑別が必要なのは、薬剤の乱用によって頭痛が続く薬剤乱用頭痛です。
薬剤乱用頭痛
薬剤乱用頭痛は、頭痛が1ヶ月に15日以上、さらに頭痛を抑える薬(トリプタン、エルゴミタン、鎮痛薬など)を10日以上の服用を3ヶ月は継続した病態です。
簡単に言えば、薬を継続的に服用したことによる頭痛です。
治療方法は、原因薬物の中止となります。
また、確立された治療方法はありませんが、バルプロ酸やトピラマートなど抗てんかん薬が治療に使われることがあります。
慢性連日性頭痛の分類方法
病院での診断によって危険な頭痛(脳疾患、血管系の疾患など)が起因していないかを鑑別する必要があります。
危険な頭痛について詳しくはこちらもご参考ください。
変容性片頭痛(慢性片頭痛)と慢性緊張型頭痛の鑑別は難しいとされ、過去の頭痛の状況も踏まえて判断されます。
持続性片頭痛は、頭痛が継続する以外に自律神経症状(目の充血、鼻水など)がみられます。
慢性緊張型頭痛と新規発症持続性連続性頭痛の大きな違いは、初めての頭痛で継続している点であり、症状は緊張型頭痛とほとんど同じです。
頭痛が続くケースにおける病院治療
それぞれに病態によって治療方法は異なります。
持続性片頭痛は、服薬(インドメタシン)によって効果的に改善されます。
慢性の緊張型頭痛および片頭痛は、中枢神経系の原因と考えられると共に精神疾患患者に多くみられることから抗うつ剤が処方されることがあります。
※頭痛患者は非頭痛者と比較すると2~5倍うつや不安神経症を併発しているという研究報告があります。
新規発症持続性連日性頭痛は、治療方法が確立されていません。
慢性的に続く頭痛が病院で改善されないのはなぜ?
慢性的な頭痛は、薬に反応して改善されるケースもありますが、色々な要因が重なっているケースも多く、薬では解決されることも少ないです。
そして、頭痛は不定愁訴(病院では異常が見当たらない症状が現れる)でも見られる症状であるため、薬物治療が中心の病院では改善が難しいのではないでしょうか。
なかには精神的な影響と片づけられることもあり、それが結果として患者が不満を抱き治療が進まないこともあるようです。
※カイロプラクテイック心には精神疾患の薬を服用され効果がなく相談にこられる人が多いです。
中枢神経機能が頭痛の原因
毎日頭痛が数ヶ月続く慢性頭痛は、中枢神経機能が原因ではないかと考えられています。
緊張型頭痛は、「筋収縮を抑制する機能」「疼痛抑制システム」の異常が指摘されています。
片頭痛では、脳幹部にある三叉神経由来という説が強いです。
また、痛みの科学では慢性的な痛みの要因の一つとして侵害可塑性とよばれる神経系の変化によって痛みが継続しています。
このようなことから、慢性的な頭痛は神経機能の評価、アプローチが重要と言えます。
しかし、病院では主に器質的な問題(画像や血液検査で異常がみられるケース)を治療しますが、慢性頭痛でみられる機能的な問題は見逃され治療が難しいことが現状です。
神経機能を改善するポイント
カイロプラクテイック心は、神経機能を評価し神経可塑性と呼ばれる神経が変化する性質を利用して慢性頭痛に対してアプローチします。
神経可塑性について詳しくはこちら
頭痛の場合は、脳幹部分が過剰に興奮(音、光、においなどに敏感となる)船酔い、車酔いしやすいなどの傾向がみられます。
また、ストレスが強いと前頭葉が機能低下すると研究報告があり、このような状態になるとさらに脳幹部が過剰に興奮し頭痛が誘発されやすいです。
そのため、脳幹部を上手く抑制できるよう前頭葉の機能を向上させる神経ネットワークに対して集中的にアプローチしていきます。
栄養も大事
体を作るのは栄養であり、神経系も例外ではありません。
また、最近では腸と脳の相互関係も複数の研究で報告され、中枢神経機能異常と考えられている疾患(パーキンソン、うつ、不安症など)に対して栄養療法の有効性も研究されています。
腸と脳の相互関係について詳しくはこちら
とくに不定愁訴のような頭痛は、栄養から考えていくと良い結果が現れることもあります。
不定愁訴と栄養の関係について詳しくはこちら
カイロプラクテイック心の毎日続く頭痛の改善方法
カイロプラクテイック心は、神経機能の評価を重視します。
また、栄養検査、自律神経検査など客観的な指標を用いて、より改善すべきポイントを明確にしていきます。
例えば、栄養では起床時のから頭痛がひどい、1日2食以下、肥満(お菓子類、揚げ物などをよく食べる)などは栄養の見直しから行ったほうが良いです。
カイロプラクティック心の評価法の1つとして、自律神経系を客観的に評価するツールを用いて、交感神経が優位なケースにおいては、施術での自律神経系へのアプローチおよびセルフケアの指導も行います。
中枢神経系の姿勢制御の問題では、姿勢反射(原始反射)、感覚機能(前庭系:バランス機能、視覚、体性感覚)などの評価が重要です。
また、これらの感覚を統合する頭頂葉、疼痛抑制系の神経経路なども評価し、問題に対してアプローチしていきます。
施術
- 機能神経検査
- 頭蓋骨の調整
- 施術
- ホームケア指導
中枢神経系の問題⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント、眼球運動、バランスエクササイズなど
末梢神経系の問題⇒筋伸長テクニック、カイロプラクティックアジャストメントなど
ホームケア指導⇒栄養、簡単なエクササイズ
自律神経系⇒迷走神経アプローチ、頭蓋仙骨療法
カイロプラクティック心は施術歴15年以上の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。
また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。
片頭痛、緊張型頭痛のページもご参考ください
頭痛のタイプによりますが、筋緊張が強い場合は施術によって一時的な頭痛緩和は可能です。
また、自律神経系に関わりの強い呼吸機能を改善させるために胸郭(肋骨、鎖骨、背骨)へのアプローチは必要となります。
栄養サポート
カウンセリング、食事記録だけでも栄養の過不足による頭痛の誘発原因(血糖値乱高下、隠れ貧血、たんぱく質不足、腸内環境の悪化など)の特定に役立ちます。
さらに血液検査から栄養状況を把握することは可能です。
栄養状況の改善によって頭痛が改善される研究報告も複数あり、栄養サポートは頭痛改善にも有効と考えられます。
詳細な栄養サポートは人によって異なりますが、大きくは正しい食生活を身につけてもらうことが大事です。
そして必要に応じてサプリメントを利用していくこと体を早く良い状態に戻せます。
カイロプラクテイック心は、栄養コンシェルジュ®2つ星の資格を取得しています。
高額なサプリメントを売ることはありませんので、ご安心ください。
感覚エクササイズ
頭痛がみられる人は、視覚機能(眼球運動、周辺視野など)や前庭系(平衡感覚、加速など)の機能低下がみられることがあります。
そのようなケースにおいては、ビジョントレーニング、前庭系エクササイズなど感覚エクササイズが有効です。
中枢神経系の問題は、その人のレベルに合わせてできるエクササイズによって神経系は活性化されやすくなります。
感覚エクササイズについて詳しくはこちら
続く頭痛の改善期間
1日でも早く改善するよう全力を尽くしますが、数ヶ月続いていると痛みを感じ取りやすい状態に神経系が変化していることが多いです。
また、栄養不良、生活の悪習慣など複数の要因が重なり合っています。
そのため、時間がかかるケースも少なくありません。
基本的には6週間(週1~2回の施術)変化の有無を観察しながら、頭痛の改善を目指します。
毎日続く頭痛を改善して快適な生活を
慢性的な頭痛を改善することは、文章で書くほど簡単ではありません。
しかし、神経機能から頭痛の原因を紐解くことで、毎日続く頭痛から解放される可能性があります。
栄養や生活習慣の見直しなどご協力をお願いすることもあるかと思いますが、一緒に頭痛を改善していきましょう。
そして、頭痛を改善して趣味を楽しみ、仕事や育児に集中できる生活を手に入れてください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害















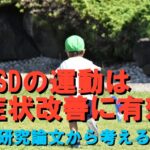






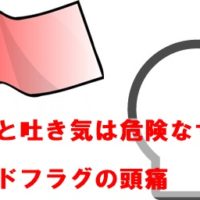





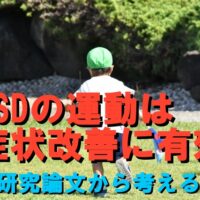








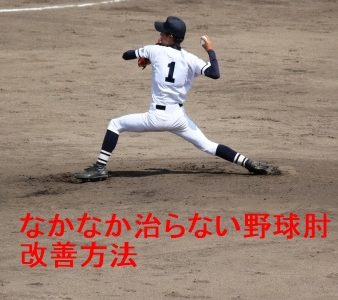

この記事へのコメントはありません。