BBIT(Brain Based Integration Therapy)は、左右の脳バランスを評価して、施術や運動療法および栄養療法などを組み合わせ、脳バランスを改善していく療法です。
とくにBBITは、こどもの発達障害に有効なモデルになります。
BBIT認定療法士であるカイロプラクティック心の岡が、BBITについて解説していきます。
発達障害についてはこちら
パッと読みたい人は見出しをクリック
BBITとは
BBITは、アメリカのDr.Melillonのメソッドをもとに吉澤DC(インターナショナル機能神経学ボード小児神経発達症フェロー)が作り上げた療法です。
吉澤DCのBBITホームページはこちら
Dr.Melillonのメソッドのコンセプトを取り入れた発達障害アプローチはBBIT認定療法士になる前から行っており、BBITでの脳へのアプローチもこちらをご参考ください。
BBITの考え方
発達障害は、自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害などありますが、BBITで診断することはできません。
なぜなら、診断は医師のみが許された行為だからです。
そのため、当然ですが診断された発達障害を覆すことはなく、「治りますよ」と断言することもできません。
BBITは、カウンセリングのときに診断名を聞くことはありますが、診断名に応じた療法はしておらず、脳機能のアンバランスを評価し改善を目的とした療法です。
脳のバランスが改善された結果、医師の判断によって診断名が外れることはあります。
また、BBIT、Dr.Melillonのメソッドでは、発達障害での困りごとが改善されている臨床報告が多くあります。
研究論文は以下の通りです。
3.2歳から22.04歳までの2,175人の個人を対象に調査が行われ、12週間のプログラムの後、原始反射は大幅に減少し、すべての運動および認知測定のパフォーマンスが大幅に向上しました。
参考文献:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.431835/full
BBITの評価方法
脳の左右差を質問票(両親への質問を含む)脳機能のアセスメント(原始反射、小脳、前庭系、大脳など)によって、脳の左右バランスを比較します。
脳の評価方法についてはこちらもご参考ください。
なぜ脳の左右バランスが崩れると発達障害の特性が現れるのか?
脳は脳梁(左右の大脳半球をつなぐ交連線維の太い束)を介して、左右の大脳半球が情報交換を行い、表現(運動、感情、コミュニケーションなど)の仕方を決定します。
また、様々な情報(視覚、聴覚、嗅覚、触覚、身体の位置感覚など)を正確に受け取り、それを脳内で処理することで初めて表現することができます。
発達障害のこどもは、何らかの原因によって左右の脳バランスが崩れ、そのことにより表現方法がそれぞれ異なり診断名が変わると考えられます。
例えば、右脳は感情や共感する能力に優位性があり、機能が低下すれば相手の気持ちがわからないことでコミュニケーションがうまくとれません。
反対に言語や数字などの優位性がみられる左脳が低下すれば、自分の気持ちを表せないことでコミュニケーションが上手くとれないこともあります。
また、「眼球運動が上手くいかないことで人と目が合わせられない」「前庭系や視覚の影響で相手との距離感がわからない」などもコミュニケーションに問題が生じます。
このようにコミュニケーション1つとっても、あるゆる神経ネットワークが影響し、脳機能が低下しバランスが崩れれば発達障害の特性が現れやすくなります。
最近では脳科学の進歩により、発達障害における脳領域の不活性状態が研究で報告されるようになりました。
BBITのアプローチ方法
脳は神経可塑性と呼ばれる構造的および機能的に変化する性質があり、BBITでは脳の可塑性を利用したアプローチを行います。
脳の可塑性を利用したアプローチは、BBITだけではなく脳疾患、脳震盪など神経系のリハビリにも応用されています。
脳の可塑性についてはこちらもご参考ください。
運動プログラム
運動や感情表現は、全て感覚入力(視覚、聴覚、関節の位置感覚、嗅覚など)から始まり、それらを脳が処理し適切な指令を出しています。
例えば、本来眩しくない光でも視覚の瞳孔調整が上手くいかなければ眩しく感じ、瞳孔調整が上手くできても正しく処理できなければ、眩しいと感じてしまいます。
他にもASDでは目が回らない(回転イスで回しても目の揺れがない)ことが研究でも報告されており、これは明らかな前庭系の問題がみられる状態です。
このようにこどもの苦手は、脳機能のエラーが生じていることが考えられます。
BBITでは一人ひとり可能な限り脳機能を評価し、こどもに合わせた運動プログラムを作成します。
栄養療法
脳の可塑性は、酸素、栄養、刺激が必要不可欠です。
そのため、日常的な下痢、便秘がみられることの多い発達障害のこどもにとっては、栄養療法も重要である臨床例が多くみられます。
脳と腸は相互関係がある(腸脳相関)ことは、複数の研究報告もあり、腸内環境の悪化は脳に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。
腸脳相関について詳しくはこちらをご参考ください。
また、腸内環境だけではなく神経系を含めた体の組織は栄養素によって作られるため、タンパク質、脂質、ミネラル(鉄、亜鉛など)必要に応じて摂取していくことをお勧めすることもあります。
生活習慣の見直し
明確な科学的な根拠は示されていませんが、電磁波やビスフェノールAなど身体に悪影響を及ぼすことが複数の論文で示唆されています。
具体的には携帯電話やプラスチック製品の使用制限などになります。
栄養療法、生活習慣の見直しを強制的にお勧めはしません。ただ、お子様の状態によっては栄養および生活習慣の見直しを行ったほうが良いケースがあることは臨床的に実証されています。
BBITの流れ
1,質問票への回答
2,カウンセリング
3,アセスメント
4,アセスメントから考えられる脳機能低下側へのアプローチおよび運動プログラムの作成
1日で全てを行うことは長時間となるため、質問票は事前に記入いただくことをお願いしています。
また、小学生の低学年、未就学児は長時間の集中力が継続しないことを考慮して、数回に分けてアセスメントを実施していくこともあります。
BBITを行う期間
基本的には3ヶ月を目安に週5回以上の療法(自宅での運動プログラムも含む)を行います。
脳の可塑性は頻度が重要であり、まずは3ヶ月しっかり行っていただくことをお勧めします。
また、食事療法、生活習慣の見直しも並行して行ってください。
なかには他の家族のこともあり、全ての療法を実施することが難しいケースもありますが、その場合は優先度の高いものから行っていただき、大きな負担がかからないように考慮させていただきます。
3ヶ月しっかりと療法を行えば全てが解決することはありませんが、よい変化がみられた場合はさらにプログラム内容に変化を加えて、さらに良い状態を目指します。
変化がみられない場合は、再アセスメント、運動プログラムが自宅で正しくできているかの確認、違う専門家の紹介など対応します。
当然ですが、無理やり継続させることはいたしませんので、ご安心ください。
BBITアプローチ方法
BBITにマニュアル的なアプローチ方法はありません。
なぜなら、脳の可塑性を促す方法は運動や施術、ビジョントレーニングなど色々あり、アイデア次第で無限にあります。
また、個人差もあり時間や回数、組み合わせは変えていかなけれが、そのこどもにとって有効なアプローチができません。
カイロプラクティック心では、施術、運動、栄養などを組み合わせてアプローチしています。
カイロプラクティック施術
小脳に正しい情報を伝えるためには、関節の可動域やアライメントは重要です。
また、頸椎や仙骨頭蓋療法などの施術は、原始反射統合を促すうえでは有効なことも多いです。
さらには下痢や便秘など消化器系が弱い子どもも多く、栄養療法だけではなく内臓マニュピレーションを行うことで内臓が活動しやすくなり、結果として消化器系の改善につながります。
- 頭蓋骨の調整
- 頸椎の調整
- 内臓マニュピレーション
運動療法
原始反射統合エクササイズ、体幹エクササイズ、有酸素運動など左右脳のアンバランスを改善する前段階となるエクササイズを優先的に行ってもらいます。
原始反射エクササイズを中心としたアプローチだけでも、目に見える変化がみられるケースは少なくありません。
ただ、年齢が高くなるにつれて、それだけでは改善されないケースも多く左右の脳バランスを改善させる感覚運動刺激を行うエクササイズが必要です。
そして、脳の可塑性を促すには、反復、新鮮、レベルアップといったように段階に応じて運動プログラムの内容を変化させることが大切になります。
また、同じ神経ネットワークに複数の刺激(小脳であれば眼球運動⁺バランス運動⁺ボール投げ)といったように複数の運動を組み合わせます。
学習障害がみられるのであれば、聴覚への刺激や認知(足し算、本を読むなど)を組み合わせて行うこともあります。
BBITでは運動療法が重要となり、こどものお悩みに合わせたうえでオーダーメードのプログラムを作成します。
BBITは、書籍にもなっておりますのでご興味のある方はご参考ください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害










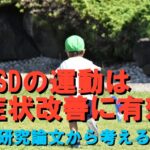






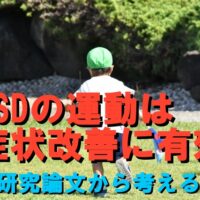


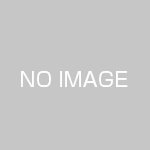
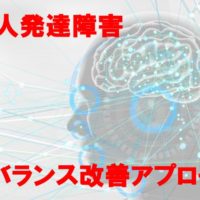











この記事へのコメントはありません。