b「発達障害あるある」をTwitterでつぶやかれていた内容を元の脳機能から紐解いていきたいと思います。
この記事は発達障害に有効なBBIT認定療法士の岡が書いています。
本日は、ADHD・ASD・LDと発達障害の種類別に、学生時代の苦手あるあるをご紹介します!
みなさんは当てはまる項目ありましたか? #発達障害 #ADHD #ASD #LD #発達障害あるある pic.twitter.com/VOfT5Mjz5b— 発達障害カウンセラーかずき@ADHD/ASD (@kazuki_honya) June 23, 2023
発達障害の種類別に分けてありますが、発達障害にみられる苦手は種類別に区切れないことも多いです。(ADHDの苦手がASDにみられる、すべての苦手があるなど)
また、発達障害と診断されていなくても、これらの苦手がみられるケースはあります。
発達障害の種類、発達障害の診断の有無にかかわらず、苦手を脳機能的に紐解いていくことで解決方法が見えてくることがあるため、何かの参考になれば嬉しいです。
パッと読みたい人は見出しをクリック
じっとしていることが苦痛
発達障害では、「じっとしていられない」「落ち着きがない」といった相談は多いです。
いくつかの要因はありますが、「原始反射の残存」「固有受容器のエラー」がみられることが考えられます。
原始反射の残存
原始反射は出生時に身につけている反射であり、一般的には1歳くらいにみられなくなります。(厳密には消失するのではなく脳でコントロールできるようになります)
原始反射の詳細はこちらをご参考ください。
反射は意思とは関係なく、ある刺激に対して体が反応するため、無意識で体が動いてしまう状態です。
例えば、原始反射の1つであるガラント反射は背中を触ることで意思とは関係なく腰が動きます。
そのため、腰を含めた背中が服や椅子に触れると体は動きやすくなるため、頭では静かに座ることをわかっていても反射によってジッとしていることが困難です。
臨床的にガラント反射のように皮膚を刺激して反応がみられるこどもは、背中以外も触られることに対して敏感であることが多いです。
反射のない大人でも不快な感覚で触れられていれば落ち着きが無くなることと同じで、発達障害の落ち着きのなさも過敏な皮膚感覚が影響していることがあります。
原始反射の残存を解決する原始反射統合はこちら
固有受容器のエラー
体には、筋肉の長さ、張力、関節の位置などを脳に伝えるセンサーの役割を果たす固有受容器があります。
このセンサーがあることで、眼で確認しなくても体がどのような動きをしているかが解ります。
一般の人でも首や背中をボキボキと鳴らしたり、足を組んだりしますが、固有受容器のエラーにより筋肉の急激な伸長、収縮、ストレッチ感など固有受容器への刺激を求めた行動といえます。
脳の成熟は20歳くらいとも言われており、脳の成熟度から考えても大人に比べて10代以下は我慢することは困難であり、幼児が動き回ることを考えれば理解はできるかと思います。
年齢と共に固有受容器を含めた神経機能も発達していくことで落ち着いて座れる時間も増えてきますが、固有受容器のエラー、他の神経系の未発達があれば落ち着いて座ることは難しいと考えられます。
このようなことから、幼児期の運動(走る、飛ぶ、掴むなど)はとても重要であり、近年のスマホやゲームの時間が多くなると運動量が減りこれらの問題は生じやすいです。
固有受容器を含めたエクササイズについて詳しくはこちらもご参考ください。
時間や期限を守れない
ADHDでは、注意欠陥の特徴として時間や期限を守れないことが多いとされています。
発達障害と診断されていない人でも時間や期限を守れないこともありますが、発達障害では何らかの原因で予定そのものを忘れてしまい社会生活に支障をきたします。
眼窩前頭皮質
眼窩前頭全皮質は、人の脳では理解が進んでいない脳領域ですが、主に以下の行動に関与していると考えられています。
- 共感、感情移入
- 社交的に適切な行動
- 長期目標に向けた行動
- 衝動の抑制
眼窩前頭皮質の働きは多くの行動に関わっていますが、長期目標に向けた行動ができなければ、時間や期限を守ることができません。
また、ADHDでは衝動抑制の機能が低下している研究報告もあり、衝動性が抑制できないうえマルチタスクが苦手が重なることで、約束ごとを忘れてしまうと考えられます。
衝動抑制のエクササイズは昔ながらの遊び(だるまさんが転んだ、旗挙、後出しジャンケンげなど)にも組み込まれています。
マルチタスク
脳の機能低下の1つに、2重課題を遂行する能力の低下があります。
二重課題(デュアルタスク)を考えるときには、「会話をしながら車を運転する」という場面がしばしば取り上げられます。 この場合、会話に注意を向けることによって運転の精度が落ちるため、事故のリスクが高まることがよく知られています。 このように2つの課題を同時に遂行する力は、脳卒中や認知症、加齢などが原因となって低下することがあります。
引用元:OGメディック
臨床的にも発達障害のこどもは、通常の足し算はできたとしてもバランス(トランポリン、片足立ちなど)をとりながらの足し算は出来なかったり、バランスをとることを止めて計算したりすることも少なくありません。
一見、簡単なようでも二重課題に難があることは多く、こどもであっても日常ではさらに複雑な2重課題をこなす必要があります。
例えば、歩きながら相手の話を理解してそれに対応した発言をすることも二重課題であり、認知症では難しいとされています。
発達障害のコミュニケーションの乏しさは、このような影響もあるのではないでしょうか。
発達障害と診断されていない人でも多くの課題をこなすことは難しく、人から言われて「そういえば・・・忘れていた」ということは少なくありません。
臨床的に発達障害のこどもは2重課題が難しいケースも多く、脳が課題をこなしていく容量が少ないことを考えれば、時間や期限を忘れてしまうことは理解しやすいように思います。
こどもで2重課題を行う場合、まずお気に入りの遊び(トランポリン、ケンケン、ブランコなど)に加えて、足し算、しりとり、今日あった出来事を話すなどを行います。
宿題ができない
宿題ができないにも色々と原因があると考えられます。
- 勉強に興味が一切もてない
- なんらかの学習障害の徴候がある
- 集中力が継続しない
ジッとしていることが苦手で集中力が継続しない場合、低学年であるほど宿題を行うことが難しいかもしれません。
また、学習障害の徴候があれば、計算や読み書きが困難であり、結果として宿題を終えることができないこともあります(学習については後述)
前頭葉
前頭葉は、発達障害と診断されていなくとも低年齢ほど脳は成熟しておらず、こどもが前頭葉の機能低下でみられる行動をとることは多いです。
そのため、宿題に時間がかかる、嫌がるといった行動は、低年齢では普通にみられる行動です。
しかし、運動や学習、社交(友達と遊ぶ、家族との関りなど)などで前頭葉を発達させていくことも重要となります。
「宿題ができない」ということに対して前頭葉の低下は以下の行動と関りがあります。
- 集中力、注意力の低下
- 新しいことを学ぶことが難しい
- 衝動や欲求を抑えることが難しい
- やる気が出ない
- 思考や単語などの整理、順序付けが困難
たとえ仕事や勉強のできる大人であっても睡眠不足や過労、ストレスによって前頭葉の機能は低下するため、ここに挙げた徴候がみられることもあるでしょう。
発達障害のこどもでは、苦手なことも多く脳へのストレスは想像を超えるものと考えられます。
臨床的に原始反射のチェックを行った時、休日は原始反射の残存がみられなかったとしても学校帰りにチェックすると原始反射の残存がみられることも多いです。
※原始反射の残存は脳疲労によってもみられます。
このようなことから、遠回りに聞こえるかもしれませんが、他の苦手を少しづつでも解消しストレスを軽減していくことも重要と考えられます。
また、リラックスできる遊び、栄養補給などで脳の疲労を一端軽減させることも大切かもしれません。
環境が変わる新学期が苦痛
環境の変化は誰もがドキドキし、5月病と呼ばれるように体調を崩すことも少なくありません。
5月病は、一般的に寒暖差や心理的なストレスなどによって自律神経が乱れやすく、身体的症状がみられやすくなります。
発達障害のこどもでも自律神経症状が伴うこともありますが、前庭系の未成熟によって新しい場所や新学期などに極端な不安をみせることもあります。
前庭系システム
自閉症スペクトラム障害のこどもは、前庭系の未成熟から目が回らない(回転いすで回しても眼振がみられない)ことが研究で報告されています。
また、反対に過敏になりすぎているケース(乗り物酔い、バランス系の運動が苦手、高いところや不安定な場所を怖がるなど)も多いです。
前庭系の感覚は重力を感じ、自分が何処にいてどのような状態にいるかを把握するために重要なシステムです。
極端に言えば、左を向いているのか、逆さまになっているかも正確に把握できないため、常に不安な状態です。
このようなことから、前庭系の未熟がみられる発達障害のこどもは、新しい教室や新しい道は不安な場所と認識しているかもしれません。
そして、不安定な場所でも慣れることで少し落ち着くことができたとしても、1年ごとに落ち着いた場所を離れなければならず、結果として新しい環境が苦手となります。
前庭系は自律神経とも関わるため、頭痛、腹痛、睡眠障害などを併発する可能性もあります。
前庭系は頭部を動かした運動であり、ブランコ、トランポリン、滑り台など工夫次第で色々な遊びを考えることができます。
集団行動が苦手
集団行動が苦手の特徴として以下のことが考えられます。
- みんなと同じように行動できない
- 人との距離感がわからない
- 音や匂いなどの感覚過敏
発達障害のこどもは、色々な要因によって模倣(人と同じ動きを真似する)が苦手であることが多いです。
模倣の苦手は運動コントロールが難しく、自分の体も思うように動かせなかったり、左右の認識が困難であったり、視覚や運動制御(固有受容器、大脳基底核など)の問題が考えられます。
多くの人の声がすることが不快、大きな音、匂いなど感覚が過敏なことが集団でいることの不安につながるケースも多いです。
視覚が発達していないことも多く、結果として人との距離感が掴みづらく集団行動の苦手に繋がることがあります。
視覚
視覚は、「何があるのか?」「どこにあるのか?」を認識しています。
「何があるのか?」⇒物の色や形などを認識するなど
「どこにあるのか?」⇒周りの景色、背景を含めて物の位置を認識するなど
発達障害のこどもは「視覚優位」「聴覚優位」と分けられることもありますが、視覚優位であっても視覚機能が優れているワケではありません。
視覚の能力が他の機能より高いため、視覚機能の能力が低くても頼らざる負えない状態であることが多いです。
視覚を詳しく解説すると文章が長くなるため割愛させていただきますが、視覚機能の未熟は人との距離感を適切に保てず、人がぼやけていたりすることも考えられます。
このようなことがあるため、発達障害にはビジョントレーニングが有効とも言われています。
暗黙のルールがわからない
ASDの特徴として社会性が自然と身につかず、具体的なルールを提示してあげることで生活しやすくなると考えられています。
では、なぜ自然と社会性が身につかないのでしょうか。
感情を読み取り行動に移す(情動)ことが社会性には必要になると考えられます。
情動はあらゆる脳領域が連動して、ネットワークとして働きます。
デフォルト モード ネットワーク (DMN)
デフォルトモードネットワークは、安静時に自分の内側に意識を向けたときに脳が示す神経活動です。
空想、未来を想像したり、他人の気持ちを考えたりする際にも発生すると考えられ、ASDはデフォルトモードネットワークの障害が示唆されています。
デフォルトモードネットワークの構成ネットワークは以下の脳領域が関わっているとされています。
- 内側前頭前野
- 前部帯状皮質
- 後部帯状皮質/楔前部
- 下頭頂葉
- 側頭葉
- 海馬
DMNの主要なノードの異常とそれらの動的な機能的相互作用が、「他者」に対する自己に関する情報の非典型的な統合、および社会的に関連した刺激に柔軟に対応する能力の障害に寄与していることが示唆されている。
記憶、学習、感情、感覚、体の認識などあらゆる脳の役割が相互作用によって、適切な社会行動に移せるようになります。
ASDのこどもの中には頭がよく、大人を言いくるめるほどの頭の回転のよさもみられます。
しかし、デフォルトモードネットワークの切り替えが上手くいかないケースも多いことが考えられ、脳疲労もしやすくネガティブな感情となり癇癪のような感情爆発になっているかもしれません。
そして、脳疲労によってデフォルトモードネットワークの活動が低下すると思考の柔軟性や記憶に悪影響がみられると考えられます。
集中して考える力のある場合でも、脳は疲労しやすく柔軟性がした状態が続けば、場面に応じた社会のルールに対応することも難しくなるのではないでしょうか。
デフォルトモードネットワークを正常化する方法としては、マインドフルネス(瞑想)が有効とされています。
低年齢ほどマインドフルネスは難しいですが、心地よいマッサージで触られているところに自然と意識が向くようにすることで代替えできる可能性があります。
音読が苦手
音読は目で文字を読み、それを理解して声に出すことが必要となります。
発達障害のこどもにおいては、眼球運動の機能が上手く働いていないことが多くみられます。
文字を読むためには、まず目で文字を追うための能力が必要であり、さらにその基礎として注視とよばれる目標物を静止画像としてとらえるために眼球を目標物に合わせることが必要です。
後頭葉
後頭葉は視覚の情報を受けてる脳領域です。
後頭葉に問題が生じると以下のようなことがみられます。
- 注視の困難(視線を保つことが難しい)
- 視覚情報から場所の特定が難しい
- サイズ、形、色の区別が難しい
- 文章の理解が難しい
- 似た色の識別が難しい
- 視界の色合いがぼやける
後頭葉は視覚に関わるため、ビジョントレーニングが有効にもなります。
ただ、眼を動かすトレーニングではなく、まずは注視していくことが初期は大事です。
そこから大きい字なら認識できる、少しの形の違いが認識できないなど苦手を理解し、それにあわせたトレーニングを実施していくことになります。
例えば、少しの形の違いが認識しにくい場合、「b」「d」を多く書いてある用紙に「b」のみをチェックしていくトレーニングを行います。
暗算・文字を書くことが苦手
暗算ができない一因としては、短期記憶(少ない量の情報を心にとめて、常に利用、引き出せる情報)として、数字を留めておけないことが考えられます。
ただ、記憶にも色々な種類があり、記憶の種類によって使われる脳領域が違います。
そのため、発達障害のこどものなかには数式を記憶することが得意で理論を理解せずに記憶中心の学習をしているケースもあります。
暗算ができない、文字を書くことが苦手に共通する問題として、頭頂葉の機能低下があります。
頭頂葉
頭頂葉は感覚情報(固有受容器、視覚、触覚などの感覚全て)を受け取り、無意識化の処理(識別、認識、解析など)を行います。
例えば、視覚の情報から数字を読み取った場合は文字を音声に変えるといった計算の行為に関わります。
また、固有受容器から筋肉や関節の情報を受けており、さらには視覚や運動に関する情報と統合することで適切な運動が行えます。
字を書くことも適切な体幹支持能力によって姿勢が保たれ、そのうえで手足を自由に動くことが可能です。
また、肘、手首、指の関節などが適切な角度を保つことで字も書きやすくなります。
頭頂葉によって適切な処理ができていないと、書くための自然な姿勢を保てず、さらには筆圧のコントロールもできず疲れやすくなります。
頭頂葉は感覚を統合しているため、ビジョントレーニングや感覚エクサイズなどを行っていきます。
脳機能は向上する
ここまで「発達障害あるある」を脳機能から紐解いてきました。
こどもの場合は、脳が未成熟であり発達段階でもあることから、苦手となる理由や背景を理解して適切な方法でトレーニングを行えば、苦手を克服しやすいです。
脳は良くも悪くも機能的および、構造的に変化する性質(神経可塑性)を持っています。
カイロプラクテイック心では、脳の可塑性を利用して苦手の理由を考え、アプローチしていきます。
実際に「宿題がはかどらない」「集団が苦手」「落ち着きがない」などの苦手が改善されるケースもみられます。
発達障害でお悩みの方は、一度ご相談ください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング
栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群
脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告
部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告













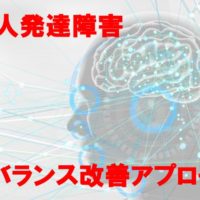
















この記事へのコメントはありません。