最近の研究によって、脳と腸が互いに影響を及ぼす関係性(腸脳相関)であることがわかってきました。
このようなことから「うつ、不安症、パーキンソン病、発達障害など」脳の影響と考えられる疾患も腸内環境の問題が示唆されるようになり、栄養療法も研究されています。
腸脳相関を大まかでも理解できると、「発達障害やうつなどに栄養療法がなぜ効果があるのか?」「反対に栄養療法で効果が現れにくいのか?」解るかと思います。
ここでは、研究論文も踏まえて腸脳相関について解説していきます。
パッと読みたい人は見出しをクリック
腸と脳の神経ネットワーク
腸脳相関には、感情やストレスによって活性化するHPA回路(視床下部⇒下垂体⇒副腎)、自律神経系が関与しています。
副腎が分泌するコルチゾールは、ストレスホルモンとも呼ばれ、腸だけではなく人の体に大きな影響を与えます。
※薬にステロイドはありますが、コルチゾールをもとに作られ長期的に服用しないことを考えれば人体への影響は理解しやすいかと思います。
自律神経系は脳からの伝達だけではなく、腸から脳へ迷走神経を介して情報が伝わります。
自律神経およびHPA回路は、腸管神経系、腸粘膜などと相互作用することによって、免疫系、運動(排便、消化)粘液の分泌などが調整されています。
腸脳相関における腸内細菌叢(腸内フローラ)の役割
腸内細菌叢は、腸内および腸管神経系だけに作用するのではなく、神経内分泌や代謝経路を介して中枢神経系に作用することが示唆されています。
腸内細菌叢とは?
腸内には、多種多様な細菌が1000種類1000兆個以上、生息しているといわれています。
腸内細菌の種類は、大きく分けて「日和見細菌」「善玉菌」「悪玉菌」の3種類です。
健康な腸内では、善玉菌が悪玉菌の増殖を抑制し、さらに有害物質を体外に排泄(排便)するのを助けます。
腸内細菌の主な役割
健康に関与する腸内細菌の役割は以下の通りです。
- 消化できなかった食物を体に良い栄養物質へ作り変える
- 腸内の免疫細胞を活性化し、病原菌などから身体を守る
- 腸内細菌叢のバランスを保ち、健康を維持する
腸内細菌叢と脳との関り
脳の発達および行動を調整することが示唆されています。(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041077/)
ほかの研究としてマウス実験ではありますが、正常な腸内細菌叢が脳の健康と病気、発達、衰弱、学習、記憶、行動に密接に関連していることが報告されています。(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101079/)
腸内の健康は、全身に影響を及ぼし、さらには精神活動や認知活動にも好影響を及ぼすと考えられます。
このような背景から、腸内環境を改善する目的とするプロバイオティクス(細菌叢を含んだサプリメント、食品)商品が販売されています。
注意)腸内環境は健康に寄与しますが、研究が続いている分野でもあるため、「○○が治る」というのは誇張しすぎです。
脳のグリア細胞と腸管の免疫系との関係
脳は1000億個以上のニューロンと、その10倍以上ものグリア細胞から成り立っていると言われています。
グリア細胞は、脳内環境の維持や代謝支援を行っており、そのなかでもミクログリアとアストロサイトが免疫調整機能を調整しています。
この脳内の免疫調整機構の活性化によって引き起こされる慢性の神経炎症は、神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病など)に関与します。
近年の研究では、腸脳相関によってパーキンソン病の神経炎症が引き起こされていることが示唆されています。(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730281/)
脳は血液脳関門によって、異物の侵入などを防いでいますが、免疫応答で増殖する細胞は血液脳関門を通過することが可能です。
そのため、腸内で慢性化した炎症が神経系にまで影響を及ぼすと考えられるようになりました。
脳からの腸への影響
脳から腸に与える影響として、心理的ストレスが腸内細菌叢のバランスを崩す要因になり、さらには腸管の透過性が変化し粘膜の免疫応答を刺激すると考えられています。
また、腸内細菌叢だけではなく粘液の量や質にも影響を及ぼし、消化活動の遅延を招く可能性があります。
腸だけでも活動はできるとされていますが、脳の制御下のもと免疫応答、消化活動が調整されていることから、胃腸障害(便秘、膨満感など)は脳機能の改善によって緩和されていく可能性もあります。
腸脳相関と疾患
腸脳相関の考えから主に以下の疾患の研究報告があります。
- パーキンソン病
- 機能性ディスペプシア
- 過敏性腸症候群
- 不安症
- うつ
- 自閉症スペクトラム障害
機能性ディスペプシア(胃もたれ、上腹部痛など)過敏性腸症候群などは胃腸障害ですが、胃や腸に検査でひっかかるような異常は見当たりません。
脳の機能異常と考えられるパーキンソン病、自閉症などは胃腸障害も併発していることから腸脳相関の考えから治療方法が模索されています。
参考文献
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114504/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817711/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384445/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7546872/
腸内環境を良くするには?
腸内環境を良くするには、規則正しい生活習慣を身に着けることも大事ですが、ここでは食事について解説します。
摂取すべき栄養素は、プロバイオティクス、プレバイオテクス、食物繊維が重要と考えられます。
プロバイオティクスは、微生物を腸内に送り込むことを指し、一般的には乳酸菌(ビフィズス菌、ラブレ菌など)です。
プレバイオティクスは、微生物の餌となるものを指し、オリゴ糖、食物繊維の一部が認められています。
順序的には、まず悪玉菌を増殖させる食事を排除し、善玉菌が増殖しやすい環境を整え(プレバイオティクス)その後に善玉菌を増殖させるプロバイオティクスを行います。
腸内環境を良くする食品
- プロバイオティクス⇒ヨーグルト、味噌類、漬物
- プレバイオティクス⇒果物、はちみつ、大豆
- 食物繊維⇒キノコ類、海藻類、グリンピース、モロヘイヤ
これらの食品は、排泄を促し善玉菌を増やします。
ただ、悪玉菌が多くなっていると考えられるケースでは、減らすべき食品もあります。
悪玉菌を減らすには?
過剰な糖質摂取(スィーツ、お菓子など)は、悪玉菌を増やし腸の炎症を促進するとしています。
他にも化学合成添加物を多く含む加工食品は、避ける必要があります。
最近では食生活が欧米化し、動物性たんぱく質、脂質を多く摂り過ぎる傾向もあり、食べ過ぎには注意が必要です。
バランスの良い食事が大事
食物繊維、プロバイオティクス、プレバイオテクスが、腸内環境を良くするキーポイントではありますが、それだけでは不十分であるケースもあります。
ストレスが多く、腸内で炎症が何度も引き起こされる(飲酒、脂肪分の多い食事、感染など)場合、炎症や酸化ストレスを抑制するΩ3系脂肪酸、酸化ストレスを抑えるビタミンA・C・Eも重要です。
また、ストレスによって副腎への負担が大きくなっているとビタミンB、ミネラル(亜鉛、カルシウムなど)良質なタンパク質(鶏胸肉、魚類など)も必要となります。
全体のバランスを考えることが結果として腸内環境を良くするため、一概に乳酸菌や食物繊維だけを食事に加えればよいとは言えません。
検査キットの活用
本来は何が足りていないかを検査することで、必要な栄養素、プロバイオティクスを摂取することができます。
最近では腸内フローラを検査し、食事のサポートアドバイスも受けることが可能です。
また、遅延型フードアレルギーを検査することで、自分の体質に合わない食物を知ることができます。
ただ、遅延型フードアレルギーについては、医学的に意味がないと考える人も少なくありません。
その1つの理由に100%確実な検査ではなく、アレルギー反応がみられた食材を制限しても症状が変わらないケースもあるからです。
検査を意味のあるものにするためには、実際に食材を制限してどうなのかを体感する必要があります。
遅延型フードアレルギーについては、こちらのクリニックがわかりやすく解説しているため、ご参考ください。
運動
腸内環境を改善するために、複数の研究を集めたレビューで運動の有効性が示唆されています。(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9368618/)
12週以上のプログラムで週3回、30分以上の中強度(軽く息が切れるくらい)の運動が有効と考えられています。
運動は小児の発達障害でも有効とされており、幼児であっても外遊びを積極的に取り入れていくことも大切です。
脳機能を適切に保つには?
腸内環境を改善させるには、脳機能も適切な状態であることが望ましいです。
脳からのアウトプットは、体を動かすような意識的なコントロールは全体の10%程度であり、残りの90%は無意識のコントロール(呼吸、心機能、内臓機能など)とされています。
そのため、脳が正常に働かなければ、無意識化のコントロールにエラーが生じ、腸脳相関にも影響を与えると考えることが自然です。
脳の司令塔である前頭葉は、過度なストレスによって機能が低下することが複数の研究で示唆されています。
前頭葉が低下すれば腸脳相関で先に解説したHPA回路のコントロールが難しく、ストレスホルモンと呼ばれる副腎皮質ホルモンが過剰に分泌し、身体に影響を及ぼします。
さらには脳幹(呼吸、血圧など生命維持に必要な中枢が集まる領域)も過剰に反応し、交感神経が高まり、音や光などの過敏性がみられます。
そして、副交感神経と関り、腸(内臓全般)の情報を脳に伝え、心拍や血圧、呼吸などをコントロールする迷走神経の機能が低下します。
脳の影響によって交感神経が高まり、ストレスホルモンが過剰に分泌されれば、腸の活動は低下しダメージが蓄積されることは想像できるのではないでしょうか。
迷走神経の低下が腸に影響を与える
ストレスは迷走神経の活動を抑制し、過敏性腸症候群や炎症性大腸疾患など胃腸障害の病態生理学に影響を与えいるとされます。
これらの疾患患者に迷走神経の活動低下はみられるため、迷走神経への刺激は腸管、腸内細菌などの回復効果の期待ができるとされています。
参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808284/
腸内環境を改善させるためには、食生活だけではなく脳機能も適切に改善させていくことが、重要であると考えられます。
ストレスコントロール
当然ですが、ストレスと感じているものが明確に解っているのであれば、それに対処していくことが大事です。
しかし、生活していくうえでストレスを無くすことは不可能です。
そのため、ストレスをコントロールする術(趣味を楽しむ、美味しいものを食べる、一人の時間を作るなど)を身に着けていくことも必要でしょう。
また、ストレスを減らすことが研究で示唆されている以下のことを習慣化していくのも一つの方法です。
- カイロプラクティック
- マッサージ
- マインドフルネス(瞑想)
- 有酸素運動(ジョギング、サイクリングなど)
- 無酸素運動(ウエイトトレーニング)
- ヨガ
- 栄養(ファスティング、ω3脂肪酸の摂取など)
- 音楽療法(モーツァルトを聞く)
- ゆっくりとした呼吸
迷走神経への刺激
迷走神経は、喉の筋肉(軟口蓋など)の活動に関わります。
また、自律神経である副交感神経と影響しあいます。
このようなことから、以下のようなことが迷走神経への刺激となります。
- うがい
- ハミング
- 風船を膨らます
- 食べ物をよく噛んで飲み込む
- 吹奏楽器を演奏する
- 冷たい水で顔を洗う
- 一時的に呼吸を止めて息をはく
カイロプラクティックでできる腸脳相関へのアプローチ
腸内環境を保つためには、栄養アプローチは重要です。
ただ、腸内の有害物質を排泄するための排便には腹腔内圧(インナーマッスルの活動)の活動が必要不可欠です。
インナーマッスルは、メディアでみられるような体幹トレーニングではなく手足を動かした身体活動によって適切に活動します。
また、呼吸の機能低下があれば、腹腔の機能も高まらず、運動にも支障をきたします。
このようなことから、カイロプラクティック施術では、胸郭および頸部の機能を改善させて呼吸の基礎能力を向上させる必要があります。
インナーマッスルは、歩行(早歩きも取り入れる)によって十分に向上させることができます。
インナーマッスルについてはこちらの記事もご参考ください。
そのため、歩行に必要な関節可動域(とくに股関節)足関節の機能向上(足底アーチ、足指へのアプローチ)をカイロプラクティック施術で行います。
脳機能の評価・アプローチ
カイロプラクティック心では、脳機能の評価および機能が低下している領域に対してアプローチします。
それぞれの脳機能の評価・アプローチ法はこちらをご参考ください。
脳機能へのアプローチとしてカイロプラクティックの有効性は、関節機能を向上させて体を動かしやすくすることです。
そうすることで、脳機能も活動しやすくなり神経系エクササイズも効果的に行えます。
腸と脳の相互作用であることを忘れない
腸脳相関の研究が発表されたことで、腸内フローラが注目され色々な症状に対しても栄養療法が行われるようになりました。
しかし、腸と脳は相互作用しているにもかかわらず、栄養のみで発達障害が良くなる、神経性疾患が良くなるとは言えないのではないでしょうか。
もちろん、栄養療法で腸内環境が改善することで症状が緩和する人もいます。
しかし、一定数改善されないケースもあるのは、相互作用であることは忘れ一方向のアプローチになっているからではないでしょうか。
まだまだ、研究段階の分野ではありますが、相互作用とされる以上は、栄養だけではなく脳機能も含めて症状の原因を考えていく必要があります。
腸脳相関の参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367209/
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害




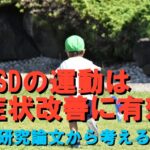






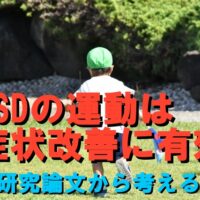



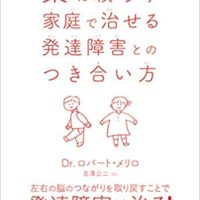











この記事へのコメントはありません。