最近では、スマホやタブレットの普及に伴い、乳幼児期からメディアを見せることが多くなっているようです。
しかし、乳幼児期は脳を発育させるために重要な時期でもあり、発達への悪影響が懸念されています。
ここでは、言葉の遅れとスクリーンタイム(テレビ、スマホなど画面を視聴する時間)について書いていきます。
パッと読みたい人は見出しをクリック
乳幼児期のスクリーンタイムの推奨時間は?
アメリカの小児科学学会(American Academy of Pediatrics)では、以下のようなことが発表されています。(参照元:https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591)
- 18〜24か月未満の子供には、デジタルメディアの使用(ビデオチャットを除く)を避ける
- 2〜5歳の子供は、画面の使用を1日1時間に制限
日本の小児科医会も2歳までのスクリーンタイムは控え、それ以上のこどもは1日2時間程度までと提言しています(参照元:日本小児医会:「子どもとメディア」の問題に対する提言)
2歳までのこどもにスマホを見せている親御さんもいらっしゃいますが、見せないことが望ましいということが小児科医の見解です。
このようなスクリーンタイムの制限に至るのは何となく体に悪そうというのではなく科学的な検証をもとに発表されており、睡眠障害、肥満、言葉の遅れなど発達に悪影響をおよぼすという研究報告が多くあります。
スクリーンタイムと言葉の遅れの研究
8〜36か月(平均= 23.5±7.18か月)の260人の子供(男性140人= 54%)を対象とした研究報告では、8〜17か月の子供では模倣ジェスチャースキルが低下し、18〜36か月の子供では言語スキルが低下する
参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32967331/
18ヶ月の子供(893人の子供(平均年齢18.7か月、男性54.1%)におけるモバイルメディアデバイスの使用と親が報告した表現力のある言語の遅れとの間に有意な関連がある
数百人単位を対象とした研究での多くが、スクリーンタイムと言葉の遅れについて関連性があると報告されています。
また、1人の研究者の主張ではなく、複数の国の研究者が自国のこどもを調査して同じような結果がみられているため、少なからずスクリーンタイムを極力無くすことがこどもの発達には良いと言えるのではないでしょうか。
メディアで言語学習はできない
6か月の乳児に中国語を聞かせる(母国語は英語の両親をもつ)ことで、中国語の習得能力を調査した研究では、以下のように報告されています。
対面形式で生の中国語を25分 x 12セッションかけて聞いた乳児は、中国語が母国語の乳児と同じような言語を認識する能力があり、中国語を聞かなかった乳児および、DVDや音声のみで中国語を聴いた乳児は、中国語の認識能力は身につかなかった(英語が母国語の乳児と同程度)
微妙な音韻要素をもつ北京語は、生後9か月の幼児がビデオを通した教育では理解を示さず、生身の人間から学習すると微妙な音韻を特定することができたそうです。
以前、「自閉症のこどもはなぜ津軽弁を話さないのか?」という記事も見かけたこともありますが、津軽弁だけではなく方言を話さない事例は耳にします。
詳しいメカニズムは解明されていませんが、メディアを中心に言語を聞く機会が多かった可能性が考えられるのではないでしょうか。
研究報告でもスクリーンタイムが長いと親との双方向性の会話が減ることが、言葉の遅れにつながるのではないかと示唆されています。
3~5歳は何を見ても良い?
小児科医師が乳幼児のスクリーンタイムについてまとめた記事があり、そこでは15分以内の教育的なプログラムであれば学習効果があるとしています。
もちろん、3歳以上であっても長時間のスクリーンタイムは推奨されておらず、個人的にも短時間のほうが良いと考えています。
言語の発育は右脳から
言葉の意味や論理は、主に左脳であり一般的に人は左脳優位と考えられます。
しかし、右脳は感情脳とも呼ばれ、イントネーションや言葉がもつ感情の意味を理解するには右脳が重要です。
そのため、乳幼児期に親からの言葉かけによる抑揚のトーンの違いを感じ取るコミュニケーション学習が始まっていると言えます。
乳幼児においてはとくにメディアではなく絵本の読み聞かせが有効です。
乳幼児はテレビ・DVDより、読み聞かせの方が言語発達に有利?[アメリカ編]
生後8〜16ヶ月児において、メディア・DVDなどへの曝露は、言語発達の低下と関連している一方で、保護者との読み聞かせ・読書が1日1回以上ある場合は、言語発達の向上と関連していたようですhttps://t.co/T3nIpcwobx
— Dr. KID (@Dr_KID_) January 16, 2021
脳機能的に考えるスクリーンタイムの弊害
乳幼児の自然な姿をどのように想像しますか?
「じっと動かずに動画を視聴する乳児」「ハイハイやおもちゃを掴んだり、動き回る乳児」
個人的には動き回る乳児が自然な姿と考えています。
発育の面から考えれば、ハイハイも歩く準備動作とも言え、寝返り、おしゃぶり、感情を表すなど全て発達の基礎を築き上げる大事な時間です。
こどもが動くことの重要性はこちらもご参考ください
テレビ視聴も年齢やプログラムによっては学習面で好影響が現れる可能性も示唆されていますが、座りっぱなしになることで神経機能が活性しにくくなります。
重力下で動くことで筋肉や関節にある固有受容器が刺激され、その情報が脳に絶え間なく伝わるため脳も活性化されます。
無重力においてはこれらが活性化されないため、無重力空間から帰還した宇宙飛行士にディレクシア(読字障害)が現れるという報告もあり、重力下で動くことが言語にも重要であることが理解できます。
長時間のスクリーンタイムが言葉の遅れに影響するメカニズムは詳細に解っていませんが、こどもが健全に成長する時間を奪ってしまっている可能性があります。
大人でも長時間のスクリーンタイムは健康被害が報告されているため、親子そろってスクリーンタイムを減らしていくことが大事ではないでしょうか。
スクリーンタイムの一工夫
スクリーンタイムが良くないことは理解できても、こどもが見たいものを無理やり辞めさせることも心苦しいのは事実です。
スクリーンタイムの問題点は、コミュニケーションをとらず、さらには動かないことです。
言い換えれば、コミュニケーションをとり、体を動かせれば脳機能的にも問題が生じにくいと考えられます。
例えば、歌や踊りをみるのであれば、一緒に歌ったり、踊ったりすることを促すことが良いでしょう。
アニメを見ているのであれば、親が話しかけながらコミュニケーションをとります。(WHOもテレビ視聴で話しかけることは推奨しています)
そして、ただ延々と見せるのではなく、終わりを意識させる(○○分になったらやめる、1つの動画を見たら終わるなど)ことも衝動を抑制するには大切です。
こどもがテレビやYouTubeを見ている間に色々と用事を済ませたい気持ちは分かりますが、大人しくしているからといって放っておくことは止めましょう。
また、こどものスクリーンタイムは大人が休む時間ではなく、こどもと一緒に過ごすことが大事ではないでしょうか。
親子の時間を楽しむ
人は、基本的にマルチタスク(複数の作業をこなす)を高レベルでこなすことが難しいです。
乳幼児ならなおさらであり、スクリーンタイムにより親子に時間まで削られます。
スクリーンタイムを短くして「絵本を読み聞かせる」「一緒に体を使って遊ぶ」「子供と一緒に一喜一憂する」など、こどもと大切な時間を有意義に過ごしてみてはいかがでしょうか。
人の一生を考えれば乳幼児期はほんの僅かな期間であり、将来抱っこしてあげたり、本を読んであげたりすることはできません。
家庭環境は人それぞれであり、余裕のない生活を強いられる方もいらっしゃると思いますが、愛するこどものために自分の時間を割いて大切に使ってください。
発達障害のご相談は受付けておりますので、ご利用ください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害






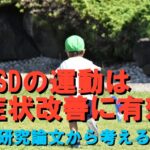












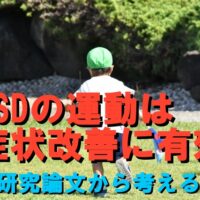










この記事へのコメントはありません。