人の体には、自分の細胞とそれ以外の細胞を見分ける仕組みがあり、それを免疫と呼びます。
そのため、ウイルスや細菌が体内に侵入しても免疫の力によって、重篤な症状を引き起こさずに済みます。
ただ、見分ける仕組みにも何らかのエラーがあると、花粉や食物など人体な無害なはずの細胞でも攻撃しアレルギー症状がみられることもあります。
このように免疫の仕組みは複雑な側面もあり、「○○すれば免疫が上がります」ということはありません。
しかし、今までの研究成果によって免疫の維持向上が期待できる生活習慣があることは解ってきました。
ここでは、免疫力を上げるための生活習慣について書いていきます。
パッと読みたい人は見出しをクリック
免疫力を上げる睡眠
睡眠は、体を回復させるだけではなく、生理機能(記憶の統合、学習などの神経可塑性、ホルモン分泌など)を調整し、免疫機能にも影響を与えると考えられています。
睡眠と免疫の関係性は、睡眠不足が免疫力を低下させるだけではなく、感染初期の免疫応答時に睡眠障害がみられるといった相互作用が示唆されています。
このようなことから、米国心臓協会と疾病管理予防センター (CDC) は、健康を維持し病気の可能性を減らすためには、最低7時間の睡眠時間が必要であると主張しています。
また、米国睡眠医学会 (AASM) と睡眠研究協会 (SRS) も7時間以上の睡眠を以下の理由により推奨しています。
定期的に毎晩 7 時間未満の睡眠は、体重増加や肥満、糖尿病、高血圧、心臓病や脳卒中、うつ病、死亡リスクの増加など、健康への悪影響と関連しています。
睡眠時間が 7 時間未満であると、免疫機能が損なわれ、痛みが増し、パフォーマンスが低下し、エラーが増え、事故のリスクが高くなります。
感染症と睡眠不足
マウスの実験ではありますが、7時間未満の睡眠で正常な免疫応答が開始されなかったと報告されています。
睡眠の減少によって引き起こされる感染症に対する免疫に関わる組織の影響として、T リンパ球の増殖の減少、HLA-DR分子の発現の減少などが観察されています。
COVID-19の研究では、6 カ国で実施された高リスクの医療従事者の睡眠習慣を評価したところ、睡眠時間が長いほど COVID-19感染の可能性が低くなり、逆に深刻な睡眠障害があると88%感染の可能性が高くなることが示されました。
ストレスホルモンと睡眠不足
ストレスを感じると、ホルモンの一つであるコルチゾールが分泌され、血糖を上昇させると共に血圧、脈拍も上昇させてストレスに対応します。
また、コルチゾールは免疫機能が働き過剰な炎症や腫れなどを引き起こさないよう、免疫抑制の作用もあります。
コルチゾールが正常に分泌されることで、一定の時間に目が覚め(体内時計を保つ重要なホルモンでもあります)ストレスに対して体を適切な状態を保たせます。
コルチゾールと睡眠不足とに関係性を調べた研究では、8時間未満の睡眠(起きている時間が17~40時間)では、コルチゾールの分泌量が上昇していました。
また、体内時計に変化(夜中起きている、普段起きている日中の時間まで寝ているなど)させるとコルチゾールの分泌量が低下しました。
この研究結果から、睡眠不足が続くことでコルチゾールが過剰分泌されれば免疫が抑制され続ける可能性があります。
体内時計に変化を与えた場合、コルチゾールの分泌低下が確認されており、体内時計が乱れると適切なホルモン分泌が行われない可能性が考えられます。
体内時計が乱れると肥満や腫瘍、糖尿病といったリスクが高まるとされています。
睡眠のとり方
推奨される睡眠時間は、年齢によって異なります。
睡眠専門医の河合医師は以下のとおりの睡眠時間を推奨しています。
何回も言いますが、小学生中学生は9ー11時間、ティーンエイジャーは8−10時間の睡眠が推奨されています。議論の余地はほとんどありません。小学生が午後8−9時に寝て午前7時に起きる。高校生が午後10時に寝て午前7時に起きれば達成。 pic.twitter.com/6vgOe5b2rS
— とにかく眠れ!河合真 (@EarlyQuarry) January 16, 2017
ここまでは7時間以上の睡眠が推奨されている研究を紹介してきましたが、理想として6~13歳以上では9~11時間、14~17歳では8~9時間の睡眠が推奨されています。
睡眠の質について聞かれることも多いですが、まずこの睡眠時間を確保することが先決です。
そのため、体内時計も正常に保つために起床時間を一定にし、そこから逆算して必要な睡眠時間を確保しましょう。
National Sleep Foundation ( NSF )では、睡眠の質を良くするために以下のことを推奨しています。
- 日中は明るいところで過ごす
- 1日30分/週5回の運動
- 決まった時間に食事
- 就寝前のアルコール、たばこ、沢山の食品を摂る、カフェインは避ける
- リラックスできるルーティンを行う
- 就寝1時間前にはデバイスを消し、静かで暗い場所で眠る準備をする
引用元:National Sleep Foundation ( NSF )
とくに日本人は、睡眠時間が短いことが指摘されています。
仕事や育児になど環境的に睡眠時間を確保することが難しい人もいるかと思いますが、可能な限り推奨されていることを実践していくことをお勧めします。
睡眠に関する参考文献
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465119/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4568388/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5567876/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5401766/
免疫力を上げる食事
「○○を食べれば免疫力UP」という宣伝はよく見かけますが、特定の食品を食べて免疫力が上がることはありません。
基本的には栄養のバランスよく、適切な量を食事で摂取していくことが大切になります。
特定の食品が免疫力を上げない理由は、免疫機能な単純ではなく多くの栄養素および腸内環境などが影響しているからです。
免疫を機能させるために必要な主な栄養素は以下のとおりです。
- タンパク質(鶏ささみ、牛モモ、豚ヒレ、納豆、カツオなど)
- ビタミンA(モロヘイヤ、人参、レバー、卵黄などレバーや緑黄色野菜に多く含まれる)
- ビタミンB6(カツオ、モロヘイヤ、ピスタチオなど魚介類、肉に多く含まれる)
- 葉酸(ほうれん草、ブロッコリー、納豆、いちごなど野菜、果物に多く含まれる)
- ビタミンB12(シジミ、レバー、アサリ、サンマなど動物性食品に含まれる)
- ビタミンC(レモン、キウイ、ピーマンなど野菜や果物に多く含まれる)
- ビタミンD(干ししいたけ、干しきくらげ、サンマなど供給源は少ないが日光浴で生成される)
- ビタミンE(モロヘイヤ、かぼちゃ、ピーナッツ、ひまわり油など植物油、種実類、魚介類に多く含まれる)
- 亜鉛(カキ、納豆、牛モモ肉などタンパク質を多く含む食品に含まれる)
- 銅(レバー、ピスタチオ、ホタルイカなど魚介類、種実類に多く含まれる)
- 鉄(レバー、シジミ、青のりなどレバーや貝類に多く含まれる)
- セレン(マグロ、カツオ、レバーなど魚介類に多く含まれる)
これらの栄養素の他にもω3脂肪酸、マグネシウム、ビタミンK、腸内環境を改善する栄養素(ビフィズス菌、乳酸菌、食物繊維、オリゴ糖など)も摂取していくことが望ましいです。
このように免疫機能を正常に保つための栄養素は多く、栄養バランスを考えた食事が必要であることが理解できるのではないでしょうか。
調理方法や合わせて摂ったほうが良い栄養素(例:鉄+ビタミンC、タンパク質+ビタミンB群など)なども考慮する必要があり、食品を食べたとしても体に吸収されていないケースもあり注意が必要です。
また、加工食品の添加物に栄養の吸収を妨げられることもあり、加工食品を抑える、ラベルをみて添加物の少ないものを選ぶなどの工夫も大切になります。
適切な量を食べることが大事
食べ過ぎは、肥満のリスクがあります。
肥満は、免疫機能であるヘルパー T 細胞、細胞障害性 T 細胞、B 細胞、ナチュラル キラー細胞の活性が損なわれ、抗体とインターフェロン-γ の産生が減少することが報告されています。
このことから、免疫機能は肥満によって低下する可能性があります。
肥満とは反対に低栄養状態は、免疫機能を働かせる栄養素が十分ではなく可能性が高く、免疫機能の低下を招きます。
日本人でも欧米ほどではありませんが、肥満は増加傾向(引用元:厚生労働省の調査)です。
また、先進国である日本でも間違ったダイエット、ライフスタイルの変化などの要因で低栄養の若い女性も多くみられ(引用元:大塚製薬)こどもは偏食による低栄養がみられる調査報告もあります(引用元:ハウス食品)
このようなことから肥満傾向がある人は「適切なダイエット」こどもや痩せている女性は「体を作るための食生活」を心がける必要がるでしょう。
腸内環境を整える
ヒトの腸管内には1000 種100兆個を超える腸内細菌が存在し、それらが腸内細菌叢を形成し腸管免疫があります。
腸内細菌叢は、多くの食品をとることで有益な細菌叢を形成するとされています。
とくにこどもは、発達段階で多くの食品を摂っていくことが大切です。
研究ではプロバイオティクス(とくにビフィズス菌、乳酸菌)が、免疫機能を改善し呼吸器感染症の発生率を減らすことが示唆されました。
日常的に下痢、便秘といった症状がみられる場合は、とくに腸内環境を整えていくことも重要ではないでしょうか。
サプリメントは利用すべき?
サプリメントは、必ずしも必要ではありません。
しかし、生活環境や食事の偏食など状況によって必要最低限の栄養素も摂れないケースにおいては、サプリメントも利用していくほうがメリットはあります。
例えば、冬や日中外に出る機会がない人はビタミンDが不足しやすいですが、食品だけで補うよりもサプリメントを利用したほうが効率的です。
女性では月経もあるため、鉄やビタミンC、葉酸、ビタミン12などのサプリメントを利用したほうが良いかもしれません。
野菜が苦手、肉が苦手といった好き嫌いもある場合は、マルチビタミン、プロテインなどで補ってあげるほうが良いでしょう。
参考文献
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31426423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723551/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8223524/
免疫と運動
運動は、健康を維持、向上させるうえで必要不可欠です。
免疫系は、運動の強度によって変化することが知られています。
中程度の強度の運動は免疫機能を向上させますが、高強度の運動および適切な休息を伴わない長時間の運動は免疫機能を低下させます。
免疫低下がみられる運動は、中程度から高強度の活動を90分間行った後です。
中程度の運動を定期的に行うと免疫機能が向上
中程度の運動は、免疫細胞、免疫グロブリン、抗炎症性サイトカインの循環が上昇すると共に、マクロファージの抗病原性活性の増加がみられ、それらによって臓器への病原体の負担を軽減します。
定期的な運動は、炎症反応とストレス ホルモンが減少し、対照的に病原体を攻撃する免疫系の細胞(リンパ球、NK 細胞、未成熟 B 細胞、単球)は増加します。
これらの要因により、適切な強度の運動を定期的に行うと座りっぱなしの人と比べて呼吸器感染症の減少と関連することが解っています。
こどもでも公園や家庭で体を使って遊ぶことは重要であり、研究では身体運動による子供の免疫細胞の成長と酸化的修復、および病気の予防が示されています。
適切な運動量は?
新型コロナウイルスと運動の研究では以下の運動量が推奨されています。
中強度の運動を週に合計150分(1日平均30分程度)あるいは筋トレなども取り入れた高強度の運動を75分間行うことで新型コロナウイルスから最も守られていた
運動や身体活動を習慣として行っている人は、新型コロナに感染するリスクが11%低い
さらに、運動をしている人は、運動不足の人に比べ、新型コロナに感染した場合の入院リスクは36%低く、重症化リスクも44%低い。
運動により新型コロナにより死亡するリスクは43%低い
中程度の運動の目安として「138ー(年齢÷2)」で算出される脈拍数となります。
日々の運動習慣によって脈拍数を上げる運動の内容は異なりますが、少し早いペースのウォーキング、ゆっくりめのジョギングが中程度になります。
当然ですが、運動習慣が継続するほど中程度の強度は上がるため、ペースを上げたりアップダウンのあるコースなど強度を上げていくことも大事です。
日常的な運動の工夫としては、普段は車を利用する近隣の施設まで自転車やウォーキング、テレビを見ながらスクワット、ランジなどのエクササイズを行うなども良いです。
WHOも、無症候性で健康な人は、大人の場合は週に150 分以上、子供と青年の場合は週に300分以上運動することを推奨しています。
参考文献
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8902492/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883243/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387807/
家族で生活習慣を見直そう
健康的な生活習慣は、最良の病気予防となります。
当然、病気に応じて服薬や外科的手術などの治療は必要ですが、生活習慣の良し悪しで治療の予後も変わるのではなきでしょうか。
病院のなかには、手術前後に運動リハビリ(術後は早ければ翌日)を行うことで予後が良いことを報告しています。(病院なので栄養バランス、睡眠時間も十分かと思います)
こどもに良い生活習慣を身につけてもらうには、まず大人が見本となる必要があります。
個人的には、幼少期の習慣が大事だと考えています。
こどもと一緒に遊んで体を動かす楽しさを教える、早く寝る習慣を身につける、家族でごはんを楽しく食べるなど家族そろって行うことで、家族全員が健康になることが、こどもも丈夫な体に発達していくのではないでしょうか。
生活習慣を最良にしていこことが、このように存在する最高の健康法であることは間違いありません。
健康を願うのであれば、まず生活習慣から!
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害




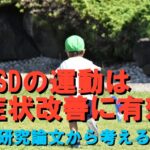









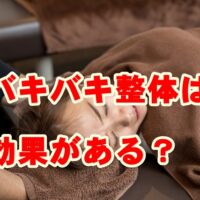


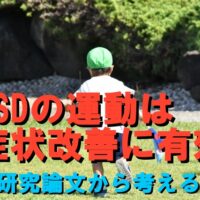










この記事へのコメントはありません。