パッと読みたい人は見出しをクリック
グルグル回転する、フワフワする、ふらつく、耳もおかしい?吐き気もある?
めまいと言っても人によって「天井や周囲がグルグル回る」「自分がグルグル回る」「フワフワする」「雲の上を歩く感じがする」「気が遠くなる」「まっすぐ歩けない感覚」など表現の仕方に違いがあります。
表現が多様なようにめまいにも種類がいくつかあり、同じ種類のめまいでも病態や原因が違います。
めまいはなぜ起こる?
人には身体にあるいくつかの感覚器を使って現在の状況を素早く感知し、それを脳に伝え、さらに脳から色々な情報が身体に伝えられる神経ネットワークがあります。
この機能があることで転倒しそうになっても転ばなかったり、目を閉じてもどのような姿勢でいるかが分ったりします。
そのため、これらの機能に問題がおこれば、どのように体勢をとっているかが認識できなくなり、結果としてフラフラしたり目が回ったりするめまいを引き起こします。
このようなことから、めまいの原因は大きく分けると脳(中枢)もしくは感覚器(末梢)の2つの問題があります。
めまいに関係するのは、以下の感覚器です。
眼球(視覚)
視覚はバランスをとるために重要であり、バランス機能の8割を占めると言われています。
そのため、目を開けて片足立ちが長くできても目を閉じると急にバランスを崩しやすくなります。
また、自覚はできませんが首を回したり、頭の位置が変わることで眼球の位置が適切な状態にコントロールされています。
この機能があることで体が傾いたとしても景色を認識できたり、真っすぐ歩くことができたりします。
何らかの原因で身体の状態と視覚のコントロールができなくなると目が振れてしまい、回転性のめまいを感じるようになります。
三半規管(平衡感覚)
三半規管は耳の奥にあります。
三半規管の中には水があり、頭の位置が変わることで水も動き、その情報を脳に伝えることでバランスを保つことができます。
また、この機能があることで目を閉じていても体がどの方向を向いているかが認識できます。
また、三半規管と眼球は常に連携しているため、三半規管の異常は眼球のコントロールも異常となり、目が振れて回転性めまいを引き起こします。
固有受容器(関節、筋肉)
関節の曲がる角度、筋肉の緊張度などを脳とやり取りすることで、無意識でも状況に応じた姿勢がとれます。(坂道、転倒しそうなときの立て直しなど)
立位では、とくに足裏の感覚(どこに圧が一番かかっているか)が重要になります。また、フワフワするめまいで多いのは頸部の固有受容器の乱れが多いと言われています。
これらの感覚器は相互作用があり、さらに正常に働くには血液循環や神経系(自律神経を含む)もしっかりと働く必要があります。このようなことから、めまいの原因は複雑化してしまうこともあります。
めまいの種類
めまいは大きく分けて回る感覚のある「回転性めまい」フワフワした感覚のある「浮動性めまい」の2つあります。
また、フラつく感覚のある「平衡障害」気を失いそうになる「前失神」色々なめまいを訴える「心因性」にも分けることができます。
回転性めまい
前庭神経に関わる末梢の問題もしくは中枢性の病的な問題によって生じることが多いです。
また、同様の問題であっても軽度であったり、症状が落ち着いてくると浮動性めまいを訴えることがあります。
脳神経の1つである内耳神経は、耳の機能である聴覚と平衡感覚を脳に伝える役割があり、平衡感覚を伝える前庭神経は聴覚を伝える蝸牛神経と合流して内耳神経となります。
このことから前庭神経の末梢は、三半規管(平衡感覚器)蝸牛(聴覚)となるため、耳の聞こえにくさ(難聴)を伴う、回転性のめまいを生じることが多いです。
ただ、難聴の自覚がなく回転性のめまいの検査をしたときに初めて難聴であることに気づくこともあります。
回転性めまいをさらに分類すると以下のとおりになります。
①再発はないが突然めまいが発症する
内耳の血管性の問題、脳出血や脳梗塞などの脳疾患、前庭神経炎の他に外傷や感染性で発症することがあります。
②特定の頭位で誘発されるめまい
良性発作性頭位眩暈がほとんどですが、頚椎性めまいでも特定の頭位でめまいが誘発されます。
③発作的にめまいが誘発される
メニエール病、椎骨脳底動脈循環不全、前庭性発作病がみられます。
回転性めまいは中枢性(脳卒中、脳梗塞など)が原因のケースもあり、今まで感じたことのない頭痛、嘔吐や吐き気、手足の麻痺などを伴う場合は、症状が治まっても早く脳の専門医に診てもらいましょう。
浮動性めまい
回転するようなめまいではなく、「フワフワする」「雲の上を歩いている感覚」と表現されることが多いです。
中枢神経と各感覚器(主に固有受容器)の連携が上手く機能していないことで浮動性めまいを発症します。
そのため、肩こりによる頸部過緊張が固有受容器を乱し、浮動性のめまいを引き起こすことが多いです。
中枢神経の問題としては、小脳疾患、脊髄の病変などがみられることもあります。
浮動性めまいは、フワフワするという感覚でもあるため、貧血、低血糖症、心循環系疾患のような全身性の問題が隠れていることもあります。
前失神
気が遠くなる、意識を失いそうな感じがする(立ち眩みに近い状態)めまいのことを前失神とも言い、脳血流の急低下や血管系、心臓系の機能低下が原因と考えられます。
不整脈
急に胸が痛くなったり、動悸と共に気が遠くなる場合は、不整脈が影響している可能性があります。
血管迷走神経反射
血管迷走神経反射は、ストレス、強い痛み,咳や排せつ、腹部の内臓疾患などによる刺激が迷走神経求心枝を介して脳幹血管運動中枢を刺激すると心拍数の低下や血管拡張による血圧低下などを引き起こすします。
そのため、気を失いそうになる前に発汗、悪心など気分が悪くなるなどの症状がみられます。
起立性低血圧
立ち上がったりしたとき、5分以内に気が遠くなる状態です。
本来なら、体位を変えても血流量を調整し速やかに脳へ血液が昇りますが、起立性低血圧はその調整が上手くいかず脳の血流不足で気が遠くなります。
原因としては自律神経の問題、糖尿病、貧血、頻脈などがみられます。
薬剤性
高血圧の人が降圧剤を飲むことで急激な血圧低下を招き、脳への血流量も低下してしまい気が遠くなります。
上記の原因の他にも過換気症候群(酸素の吸いすぎた状態)脱水(循環障害になるため)が原因となることがあります。
平衡感覚の障害によるふらつき
起立時や歩行時のふらつきの訴えは、平衡感覚の障害がみられます。
先に説明した感覚器(目から視覚系、三半規管からの前庭神経系、手足からの体性感覚系)からに情報が脳に上手く伝わっていないことで、バランスがとれずにフラフラしてしまいます。
反対に脳が情報を上手く受け取れない(小脳、大脳の病気)ケースもあります。
高齢者になるとこれらの問題が複数絡んでふらつきを打ってるケースが多いです。
心因性によるめまい
色々なめまい感を訴えます(回転性、平衡感覚の問題、浮動性、前失神)
うつ症、ヒステリー性神経症、不安症候群(特定の人や特定の場所にいくと症状が現れる)にめまいが現れることがあります。
持続性知覚性姿勢誘発めまい
2017年に正式な診断名とされた、新しい概念の慢性的なめまいです。
2017年までは不定愁訴のめまい(病院では異常が検出されないめまい)であり、治療方法が確立されていません。
詳しくはこちら
めまいを感じたら?
めまいは脳の病気が原因ということがあるため、どのようなめまいでもまずは病院を受診しましょう。
とくに吐き気、頭痛、麻痺が伴う場合は、なるべく早く脳の専門医に診てもらってください。
そのような症状がなければ、緊急性は低いため、症状の発症しやすい状況、併発症状、めまいの持続時間などを整理して答えられるようにしておくと良いです。
回転性めまいは耳鼻科、他のめまいは神経内科になります。
詳しくはこちらの記事をご参考ください。
めまいを日常生活から対処する方法
めまいは、再発する病態(良性発作性頭位眩暈、メニエールなど)もあります。
また、めまいの要因の中には心因性(自律神経の問題)循環不良がみられます。
そのため、めまいの予防や対処法の1つとして生活習慣や食生活を改善することが大切です。
水分をしっかり摂る
水分不足は、脱水による前失神がおこるだけではなく、血液循環不良の一因となります。
なるべく水で1.5~2リットルを目標に摂取していきましょう。
コーヒーや緑茶にはカフェインがが含まれているため、睡眠不足や利尿効果による水分不足を招きます。
スポーツ飲料は糖分が多すぎます。
このような理由からなるべく水で水分補給を行ったほうが良いです。
姿勢を変える
良性発作性頭位眩暈は再発性のあるめまいですが、ある研究では同一姿勢(横になってテレビを長時間みる、前かがみの作業が続くなど)を保持する人に多く見られたそうです。
神経機能の問題から見ても座りっぱなし、寝続けることは機能低下を招くため、運動が嫌いな人でも同一姿勢は30分までとし、同じ作業をするにしても姿勢を変えることが大切です。
運動をする
神経機能は運動によって向上する側面もあるため、運動不足の人は簡単な運動(ラジオ体操、ウォーキングなど)から始めてみましょう。
たばこの吸いすぎに注意
喫煙は、血液循環を阻害する要因になります。
生活のリズムを整える
生活にリズムが不規則であると、自律神経も乱れやすくなります。
とくに病院では原因が解らない場合は、自律神経の乱れの影響も考えらるため、心当たりのある人はまず起きる時間を一定にすることから始めましょう。
栄養バランスのとれた食事を摂る
貧血、低血糖は浮動性のめまいの原因にもなります。
なかには極端なダイエットによる偏食で体調を崩すこともあるため、ダイエットでも栄養のバランスを考える必要があります。
糖質制限やグルテンフリーを取り入れる人もいますが、一般的には大事な栄養素でもあるため、極端な制限はやめましょう。
めまい改善は知ることから始まります
めまい1つとっても色々とあることが、ご理解いただけたのではないでしょうか。
そのため、めまいの種類によって受診するべき病院や治療方法が違います。
さらに原因は多岐にわたるため、その人のめまいに合った改善方法を実行しないと効果が現れにくいです。
めまいの原因が早く突き止めるためにも、どのようなめまいなのか?(グルグル回る、歩く時だけふらつくなど)
どのような状況でめまいが起きるのか?
(起き上がるとき、前触れもなくなど)どれくらいめまいが続くのか?(数秒、数日など)などをしっかり整理して伝えるとめまいを改善させる手掛かりが見つかりやすいです。
カイロプラクティック心は機能神経学、原始反射など神経機能の評価を行い、原因にあわせたアプローチ、セルフケア指導を行いめまいに対応させていただきます。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害




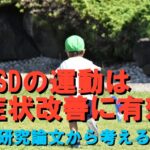









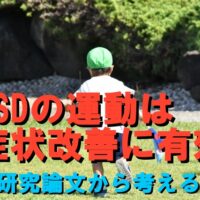





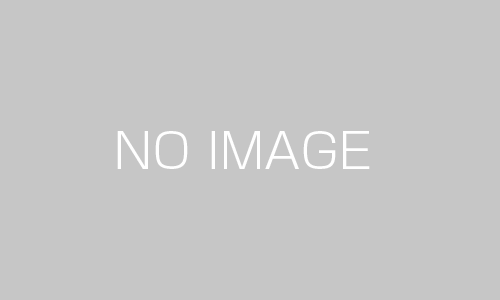




この記事へのコメントはありません。