パッと読みたい人は見出しをクリック
本当に変形していることで膝を痛めていますか
レントゲン(X線)で診断された変形性膝関節症(OA)の患者数は、以下の研究調査から2000万人を超ることがわかりました。
40歳以上を対象として有病率を推定すると, 膝OAの有病率は男性42.6%, 女性62.4%であり, わが国のX線で診断される膝OAの対象者数は2,530万人(男性860万人, 女性1,670万人)となった。
参考文献⇒https://med.m-review.co.jp/article_detail?article_id=J0002_2401_0039-0042
しかし、膝の変形無症状の人にもみられ、変形性膝関節症の所見がみられる20%にしか自覚症状が現れていないことも疫学調査でわかっています。(大森豪、古賀良生ほか 変形性ひざ関節症に対する疫学調査から引用)
このように変形性膝関節症と診断されるケースは多いですが、それが痛みに直結しているとは限らず、膝の痛みの原因は、関節の運動障害、筋肉の関連痛、循環障害など多岐に渡ります。
このようなことから、本来なら膝の変形がみつかったとしても他の膝痛の原因を精査する必要があります。
ここでは、膝の変形が必ずしも痛みの原因ではないことを詳しく解説していきます。
変形性膝関節症の基礎知識
変形性膝関節症は英語で「Osteoarthritis」と言うため、「OA」と略語が使用されることがあります。
病態として、膝関節の表面を覆う軟骨がすり減り、骨の変形がみられ炎症や機械的刺激によって痛みが発生します。
大別すると1次性と2次性に分けれます。
〇1次性変形性膝関節症
明確に原因が特定できないない加齢、性別、肥満、骨格のアライメント異常(O脚、偏平足など)などによって発症。
〇2次性変形性膝関節症
外傷や病気(骨折、靭帯損傷、関節リウマチ、半月板損傷など)などが原因となり発症。
一般的な変形性膝関節症の診断方法
レントゲン(X線)診断が一般的です。
レントゲンの所見としてグレード0~4に分類されます。
- グレード0⇒異常なし
- グレード1⇒骨棘形成の始まり
- グレード2⇒中等度の関節間隙の狭小化と軟骨化骨硬化
- グレード3⇒50%以上の関節間隙の狭小化、広範囲に及ぶ骨棘形成
- グレード4⇒関節破壊、関節間隙の消失、脛骨への軟骨化骨硬化拡大
変形がみられる部位により膝蓋大腿型、大腿脛骨型(内側型、外側型)に分類され 日本では約90%が大腿脛骨内側型です。
※O脚が多いことが起因していると言われています。
最近ではMRIの画像診断によって関節軟骨の評価もできるようになり進行リスクを把握できるようになりました。
研究論文はこちら⇒https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20953925
変形性膝関節症の症状
初期では、長距離歩行後、歩行開始時、起立や座る動作などで膝に痛みが現れることが特徴的です。
進行に伴い、夜間痛や安静時痛も現れることがあります。
また、朝方に痛みや動きの固さを感じ、人によっては午後には症状が軽くなることがあります。
炎症が生じると、水腫(膝に水が溜まると表現される)が発生し痛みを伴います。
関節の変形が進行すると明らかにわかる外反変形(X脚)内反変形(O脚)となります。
変形が進行する原因
明らかな原因は分かっておらず、遺伝性とも言われています。
一般的には、加齢に伴い慢性的に刺激が繰り返され(軟骨の損傷、摩耗が日常生活から繰り返されている)関節軟骨内のプロテオグリカンの変性が生じ、「水分含有量の減少」「関節軟骨の機能低下」により、関節の変形が進行するとされています。
また、先に紹介したMRI画像の研究報告では、骨髄異常を認め拡大していくと進行していくことが多いとされています。
一般的な病院(西洋医学)治療
保存療法(手術以外)と外科的手術の大きく別けられ、第一選択は保存療法です。
保存療法で効果がみられない場合において、手術が適応となります。
薬物療法
ヒアルロン酸注射が多く行われ、1週間に1度を5回繰り返すことが一般的です。(1本2,000円前後)
関節軟骨の成分でもあるヒアルロン酸によって軟骨の保護、修復のほか鎮痛効果、膝がスムーズに動かせるなどが期待できます。
炎症が認められる場合は、非ステロイド性抗炎症薬(ロキソニン、アスピリン、ボルダレンなど)が処方されます。
炎症が酷い場合は、ステロイド剤も効果的ですが副作用も強く現れることもあり、繰り返して打つことは少ないです。
薬物療法は効果の確認されている治療方法ですが、効果がみられないケースがあります。
順天堂大学では、以下のように報告されています。
炎症は初期から進行して手術を必要とした患者さんまで、どの段階においても痛みや症状に関連するのですが、消炎鎮痛剤のような薬が効果を発揮する炎症の原因因子は、初期から進行していくと増加するのではなく、かえって減少していくことなどを明らかにしました。
出典:順天堂大学整形外科・スポーツ診療科
薬物療法も効果がみられないケースがあることは、知っておいたほうが良いのではないでしょうか。
痛みがあまり変化しなくても抗炎症薬を服用し続けても効果は期待できず、反対に薬の副作用の問題が生じる可能性があります。
リハビリ(運動療法)
初期から中期程度であれば、運動療法により痛みが緩和するケースが多いです。
リハビリ内容は、病院によって違いますが膝周辺(大腿四頭筋、内転筋群など)および臀部(大殿筋、中殿筋)の筋力トレーニング、ストレッチによる関節可動域の回復が主として行われます。
また、手術が適応されたケースでも日常生活が送れるよう、筋力トレーニング、関節可動域の回復の他、日常動作の指導も行われます。
生活指導
痛みのある動作の禁止(正座、しゃがみ込む動作など)や減量を指導などが行われます。
変形性膝関節症は、BMI(体格指数)の増加が増悪させる研究報告もあることから、痩せることを指示されることが多いです。
個人的な意見としては、体重減少による膝への負担軽減にはなると思いますが、栄養の偏りを改善することのほうが好影響を及ぼすと考えられます。(ただ、結果として減量にはつながります)
痛みのある動作を行わないことは重要ですが、運動を禁止するような伝え方をする医者もおり、運動療法が効果的であることと矛盾しています。
完全に正座やしゃがむことを止めるのではなく、痛みのない範囲で積極的に運動、ストレッチを行い、痛みのない動きを減らしていくほうが良いです。
手術
①関節鏡手術
けば立った関節軟骨や傷んだ半月板を切除します。
痛みの軽減が長続きしないことが多いため、最近ではあまり行われな術式です。
①高位脛骨骨切り術
重度の変形性膝関節症にも適応されますが、 脛骨大腿関節の内側の変形に限局し可動域制限が少ないことが条件となります。
②人工膝関節単顆置換術
前十字靭帯断を残して、内側あるいは外側の関節面のみを人工関節に置換します。
③人工膝関節全置換術
関節破壊が進行した重度の変形性膝関節症が適応となります。
手術のリスクとしては深部静脈血栓症、感染症もあるため、重度になる前に治療をおこなうことが大切です。
当然ですが、手術後すぐ日常に復帰できないため、リハビリが行われます。
仕事や日常生活に戻るまでの経過は個人差もありますが、1ヶ月後(退院は2~3週間程度)を目安に行われます。
前述したように変形だけが痛みの原因ではないため、手術後も膝の痛みを再発すケースがあります。
変形の進行状況にもよりますが、しっかりと保存療法を行ったうえで手術の判断をした方が良いでしょう。
膝の痛みは変形だけが原因ではありません
膝の変形状況によっては、膝の変形が痛みの原因となり手術が最適な治療になることはあります。
しかし、画像で骨の変形がみられたからといって、痛みの原因にするには安易すぎます。
膝の痛みを訴えていないバスケットボール選手の膝をMRIで画像診断したところ、関節軟骨の損傷が以下のとおり認められています。
無症状のNBA選手20人(両膝)をMRI撮影をしたところ関節軟骨の損傷が47.6%認められました。
膝の痛みの原因が「関節軟骨がすり減っている」と言われることも多いです。
しかし、この研究報告のように膝に痛みを訴えてなかったとしても何らかの損傷はみられるということです。
ちなみに関節軟骨に痛みを感じる神経は存在しないため、多少の変形で痛みの原因にはなりません。
一般的には、画像診断(レントゲンのみ)で変形性膝関節症と診断されることが多いです。
ただ、このような研究報告がある以上は、「膝関節の変形=痛み」とは言えないのではないでしょうか。
変形性膝関節症には運動療法が良い理由は?
単純には、筋肉が活動することによって関節同士の衝突が減ると同時に痛みも消失していくことが考えられます。
また、痛みを誘発する原因が取り除かれれば炎症も治まるため、炎症による痛みも消失していきます。
とくに初期~中期にかけては運動療法が有効とされているため、40~50歳代であれば膝が痛いからと言って不必要に運動を中止せずに痛みのない範囲で膝を動かしてあげることが大切です。
このように変形性膝関節症と言っても、痛みの原因は筋肉の活動量の低下や関節の運動障害であるケースも少なくありません。
運動療法に効果がみられない?
膝を動かす筋肉は複数あると共に、歩行という運動をみれば膝の負担を減らすためには体幹(腹筋、臀部周辺の筋肉など)や腕の振り方、足関節(偏平足、過去の捻挫など)なども含めて評価して、適切な運動プログラムを実施したほうが効果的な人もいます。
そのため、運動はしているけどなかなか膝の痛みが変らない人は、全身を評価した適切な運動プログラムが行われていない可能性があります。
また、変形性膝関節症は中高年に発症しやすい疾患であり、長年の身体の使い方のクセが必ずあります。
それが、結果として膝を痛めやすい動きを日常生活で繰り返し、痛みが軽減しないことがあります。
このような場合、動き方を補助してあげるだけでもしゃがむことが楽になることもあります。
運動療法も自己流やただ筋力をつければ良いだけではなく、全身を評価して一人ひとりにあった運動プログラムを実施することが望ましいです。
変形性膝関節症はカイロプラクティックで対応できます
カイロプラクティック心では、早く痛みを軽減してもらい快適な生活を送ってもらうためにも、必ずセルフケア方法や日常生活のアドバイスをさせていただきます。
病院では「階段の昇り降りを減らすように」「しゃがむ動作は止めるように」など指導されます。
しかし、運動療法が効果的ということが明らかになっている以上は、「痛みのない範囲」が大前提ですが、特別な運動制限はさせずに積極的に運動してもらいます。
まず、階段の昇り降りやしゃがむ動作ができないと日常生活では、かなり不便に感じるのではないでしょうか。
また、運動しやすいようにカイロプラクティック心では、筋機能をチェックして筋機能の回復を目的とした施術及びセルフケアを指導しています。
このような取り組みにより、病院では禁止されていた運動ができるようになることも少なくありません。
病院で変形がみつかると「もう治らない」と諦める必要はなく、手術以外の方法でも痛みなく快適な生活を送ることも可能なケースも多いです。
また、仕事を長期的に休めない50~60代は、適切な処置で手術を回避し、退職後に手術することも選択肢の1つになるのではないでしょうか。
変形性膝関節症と診断されても「自分の脚で歩き続けたい」「登山や旅行などを楽しみたい」「孫と一緒に遊びたい」などの想いのある人は、カイロプラクティック心にご相談ください。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効
発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで
スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】
更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害


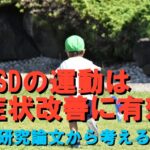




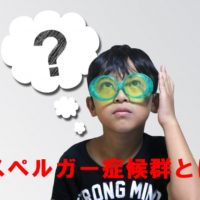



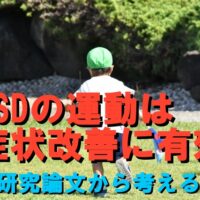










この記事へのコメントはありません。