パッと読みたい人は見出しをクリック
パニック障害は気のせいではなく脳の機能異常
パニック障害の発作は、1時間以内に治まるため病院で診てもらう頃には異常が見当たらず「気のせい」と告げられることもあります。
しかし、当然ながらパニック障害は気のせいではありません。
以前は、心因性が主原因と考えられていましたが、最近では脳の研究が進み、脳の機能異常が有力視されるようになっています。
ただ、現段階ですべてが解明されてはおらず、「心因性」「社会性」などの要因も影響し合っていると考えられます。
また、脳異能の異常と言っても身体は相互作用し、バランスを取り合い健康を維持しようとするため、脳以外の問題(栄養、内臓など)も解決することで脳の機能異常も正常に戻りやすくなります。
ここからはパニック障害の原因について考察も踏まえて解説すると共に、パニック障害から身体を守るために自分でできることをご紹介します。
カイロプラクティックトライアングル
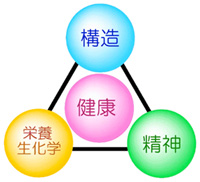
これをパニック障害の脳の機能異常に置き換えて説明します。
脳も単独で機能しているわけではなく、栄養や酸素などが正常に供給されることで機能しています。そのため、仮に脳の機能異常が原因と特定できたとしても他の働きも重要と言えます。
このように大きな原因は1つかもしれませんが、その周りに複数の原因が存在し、それらに対応していくことも大切です。
パニック障害の原因
パニック障害の原因と有力視されている脳機能およびその他に考えられる原因について解説していきます。
脳の機能異常
パニック障害は、脳幹(青斑核)、大脳辺縁系(偏桃体)、大脳(前頭葉)が関与していることが研究で解ってきました。
脳幹の青斑核の機能
ノルアドレナリンの分泌される場所で、本来なら危険や不安を感じた時に分泌されます。
パニック障害では、危険のない場所でも大量にノルアドレナリンが分泌されるという誤動作がおきていると言われています。
偏桃体の機能
快、不快、不安、恐怖など情動の中枢であり、大脳、脳幹、視床下部などさまざまな脳の組織に働きかけます。
働きかける組織には、自律神経や呼吸中枢などもあるため、不安や危険を察知した情報は、無意識に呼吸や心拍などに変化がみられたりします。
※偏桃体は、主に予期不安に関与します
前頭葉の機能
大脳皮質の一部分である前頭葉は、記憶や情動、運動など幅広い情報集め、コミュニケーションを含めた行動をコントロールします。
※前頭葉は、主に恐怖的回避(広場恐怖)に関与しています。
パニック障害の脳内は?
これらの脳の働きをパニック障害のメカニズムに当てはめるとパニック障害の発作は、何らかの原因により青斑核からノルアドレナリンが過剰分泌されます。
そして、その情報が偏桃体に伝わり不安や危険を感じると共に自律神経に働きかけ、めまい、息苦しさ、動機などパニック症状の発作が起こります。
原因の分からない発作にいつ襲われるかという不安が常につきまとうことで、偏桃体も常に活動状態となり予期不安に発展すると考えられます。
前頭葉は発作の記憶が残るため、発作をおこした場所の恐怖や人混みで発作が起きたときの不安を考えてしまい広場恐怖となると考えられます。
情動系の神経回路の存在意義
脳幹、大脳辺縁系(偏桃体を含む)、前頭葉は、大脳基底核を介して辺縁系ループを形成します。
辺縁系ループの機能を簡単に説明すると 情動、感情の表出、意欲など精神活動に関与します。
正常に働けば、危険や不安を感じた時に自律神経に働きかけ適切な身体の反応をおこし、行動ができると共にその不安や危険を記憶として学習することで今後の危険管理や備えにつながります。
パニック障害は、生活に必要な脳機能が誤動作を引き起こし症状が現れます。
脳内神経伝達物質のアンバランス
脳内神経伝達物質は、数種類あり様々な刺激に対して神経回路を繋ぐ役割があります。
「感情」「精神面」「記憶」「運動機能」など人体の重要な機能に深く影響をあたえるモノアミン神経系の三大神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリン)のアンバランスがパニック障害に関与しています。
パニック障害では、先に説明した脳幹の青斑核から分泌される不安や恐怖を感じる神経経路を繋ぐノルアドレナリンを抑えるセロトニンが不足していると考えられています。
また、GABAという脳内神経物質は数多くの興奮性の神経を抑える脳内神経伝達物質ですが、これも不足すると不安が抑えられずパニック障害を引き起こすと言われています。
セロトニン
精神の安定、ノルアドレナリンやドーパミンの暴走を抑え、呼吸や歩行などの運動機能にも関わります。
分泌不足は、うつやパニックを引き起こしやすくなり、過剰に分泌されるとセロトニン症候群(震え、発熱、精神の不安定など)を引き起こすことがあります。
ドーパミン
快楽を司る報酬系と言われ、向上心やモチベーション、学習能力、運動機能にも関わります。分泌が不足すると物事の関心が薄れ運動・学習・性などの機能低下につながることがあります。
反対に過剰に分泌されると依存症(ギャンブル・アルコール・過食など)や統合失調症を引き起こす可能性があります。
ノルアドレナリン
ドーパミンが合成されノルアドレナリンとなります。
生存本能を司り、ストレスに反応し「怒り」「恐怖」「不安」などの感情を起こし、交感神経を刺激して心身を覚醒させます。
分泌が不足するとうつ状態(気力、意欲などの低下)となり、過剰に分泌されるとイライラしたり、キレやすくなったり躁うつ状態を引き起こします。
セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリンの関係性
ドーパミンは欲望という形でストレスを生み、正常であればモチベーションになり意欲的に行動しますが、暴走すると普通の刺激では満足できな状態(依存症)になります。
ノルアドレナリンは、精神および肉体的に不快なストレス(寒い、つらい、悲しい、痛いなど)に反応し、感情(怒り、不安、恐怖など)を起こすと共に交感神経を刺激して身体と脳を興奮させます。
そのため、ノルアドレナリンの過剰分泌は心拍や呼吸の変化、発汗など急激な身体の過活動の状態となるパニック発作を引き起こします。
この過剰分泌を抑えるためにセロトニンの分泌が重要となり、正常な状態ではセロトニンとドーパミン・ノルアドレナリンが拮抗し、精神を安定させつつ、モチベーションを維持しながら意欲的に物事に取り組めます。
ストレス
不快なストレス(人間関係、仕事や育児などの悩みなど)では 視床下部、偏桃体、青斑核を刺激し、ノルアドレナリンが継続的に分泌されます。
それに対抗するためにドーパミンも分泌させ食事や運動をしたり、アルコールやタバコなどで快感を得てストレスを解消することができます。
脳内神経伝達物質のバランスを保ちながらストレスを解消できている間はよいですが、セロトニンの分泌量が相対的に低下すると、パニック障害の原因となります。
幼少期に親と離別、虐待などとも関りがあると言われています。
個人的な見解ではありますが、幼少期のセロトニンが分泌されている体験が関わっていると考えられます。
幼少期に母親に愛おしく抱かれているときは、セロトニンが分泌されこどもは気持ちよく抱かれています。
その感覚がわからないと刺激を求める(ドーパミンを求める)ことで心身を安定させようとし、どんどんと刺激的なこと求め、結果としてセロトニン不足に陥りやすいと考えられます。
前頭葉の機能低下
ストレスは、前頭葉の機能低下がみられることが研究報告されています。
前頭葉は、他の脳領域と相互作用し抑制的に働き、脳をコントロールする中枢です。
そのため、ストレスにより前頭葉が低下すると、脳を抑制的に制御できないため、自律神経が過剰に働いたり、脳幹が過剰に興奮してしまいます。
それが結果として、脳の機能異常として現れます。
遺伝性
パニック障害患者の親近者(親・兄弟)は、パニック障害を発症リスクが高いとされています。
栄養・内臓起因
セロトニンの生成は、トリプトファンという必須アミノ酸、炭水化物、ビタミンB6などの栄養素が必要です。
トリプトファンは体内では作れないため、食事で摂取しなければいけません。
栄養は摂れていても内臓(とくに腸)の働きが低下することで、栄養が身体に十分吸収されないこともあります。
栄養不足、内臓疲労により、セロトニンが不足しパニック障害を引き起こすことが考えられます。
最近では、腸と脳の相互作用(腸脳相関)があることが研究報告され、精神疾患も腸内環境の問題が示唆されています。
腸脳相関について詳しくはこちら
https://c-cocoro.com/hattatsushogai/gut-brain-axis/
性格・性別
女性は、男性に比べ2倍の発症率とされています。
「真面目」「常の不安を感じている」「心配性」「神経質」など性格によっても発症率が違うとされています。
このようにパニック障害の原因はいくつかの要素があり、複数が影響し合っています。
自分でできる対処法(生活レベルを維持する)
パニック障害の発症後は、寛解と増悪を繰り返す慢性状態が一般的です。
また、他の精神障害の併発(うつ、依存症など)することも多く、症状を長引かせる一因となります。
そこで問題となるのが生活に支障をきたし、仕事や生活が維持できなくなることです。
症状が軽くなり始めたら、少しづつ自分で対処していく方法を実践していくことも現状より身体を良くしていくためには大切なことです。
生活習慣の見直し
パニック障害は、セロトニン量の低下がみられます。
そのため、セロトニンを増やす習慣を日常に取り入れることで再発予防、症状の寛解が期待できます。
セロトニンは、朝日を浴びることで分泌されます。
また、リズム運動(ガムをかむ、歩くなど一定のリズムを刻める動き)も良いとされています。
脳の機能を維持するためには、古いたんぱく質を除去し、新しいたんぱく質を入れ替える必要があります。
この作業が最大限に発揮されるのが睡眠中であることが解っています。
良い睡眠をとるにはメラトニンが必要であり、メラトニンの生成する材料になるのがセロトニンです。
睡眠をとって脳機能を維持向上させるためにもセロトニンが必要になります。
朝に起床し、リズム運動を取り入れ夜は眠ることを習慣化できるようにしてみましょう。
食生活の見直し
腸内環境と脳内のセロトニンに着目した研究では、お腹に菌が住んでいないマウスと大人になる前に外から腸内細菌を移植したマウスを比較しると後者のほうがセロトニン濃度が増加していることが示されました。
この研究から腸内環境を整えることがセロトニンの安定供給には大切であることが解りました。
腸内環境を悪化させる原因としては以下のことが挙げられます。
- 抗生剤、ホルモン剤の長期投与
- 刺激物の摂取(唐辛子、カフェイン、人工甘味料など)
- 細菌などが多くつく食物(古い食べ物)
腸内環境を悪化させたり、内臓を疲弊させたりしているケースは、食べ過ぎもしくは身体に合わないものを摂取している人が多いです。
そのため、まずは腹6~8分の食事量を習慣化させましょう。
そして、食べた食品を記録し、体調と照らし合わせて不調を招く食材があれば、食べないことが望ましいです。
マインドフルネス
不安を感じる方の多くは現在ではなく、起きてもいない将来について考えすぎることがあります。
マインドフルネスは、「今を感じる」瞑想方法でもあります。
また、リズムよく呼吸を繰り返すことは、セロトニン分泌を増やすことにもなります。
マインドフルネスにも方法がいくつかあり、ネットや書籍でもマインドフルネスの情は手に入るため、不安を感じる方は一度お試しください。
ストレスについて
悪いイメージのあるストレスですが、広い意味では良い刺激(楽しい、温かい、涼しいなど)もストレスです。
このようなことからストレスは、良くも悪くもなく生きていく上ではあって当然のものです。
ストレスに打ち勝つ方法や無くす方法などの情報が溢れかえっていますが、実際にストレスがなくなることはありません。
仏教を開いたお釈迦様ですら、6年の苦行の末に打ち勝つことができず瞑想(ここでも紹介したマインドフルネス)で精神状態を調和させることにたどり着きました。
ストレスに打ち勝ったり、無くしたりする努力ではなく、どう調和して身体反応を正常に戻すかが大事です。
そのために前述した対処法のほか、選択(ストレスがかかる場所を避ける、ストレスになる人と会わない)適応(慣れる、趣味や一人の時間をつくる)順応(対応策をつくる)などストレスを感じることを突き止め、自分をコントロールすることのほうが重要ではないでしょうか。
カイロプラクティック心にも頼ってください
パニック障害は、内科的な異常が見当たらないため「気のせい」とされることも多く、周りの理解も得られないと本人がとても苦しい状況です。
そして、正しい治療を受けれず、慢性化した頃に治療を始めても長引くことがあるそうです。
パニック障害治療は、病院の薬物療法と心理療法が有効とされています。
しかし、それでもなかなか変化がみられなかったり、薬を減らしたいという人もいます。
そのような人は、カイロプラクティック心がサポートさせていただきます。
カイロプラクティック心は、機能神経学で脳を含めた神経系の評価を行い、それを基にアプローチさせていただきます。パニック障害は、脳の機能異常と言われているため、このようなアプローチ方法が身体が変化するキッカケにもなります。
この記事に書いた原因、対処方法も参考にしていただき、今より快適な生活ができるようになっていただければ幸いです。
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 更年期障害2024年4月24日更年期障害
更年期障害2024年4月24日更年期障害 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング
栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群
脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告
部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告








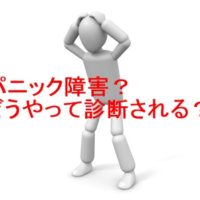









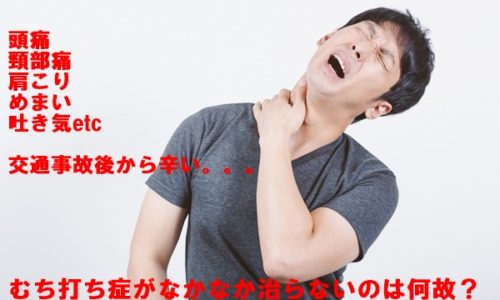

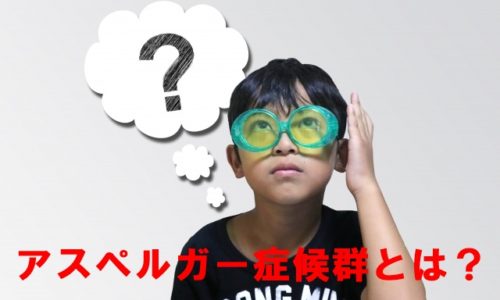

この記事へのコメントはありません。