線維筋痛症は、原因不明の慢性的な痛み、こわばりがみられます。
痛みは広範囲に及び3ヶ月以上続き、多彩な随伴症状(睡眠障害、うつ、倦怠感、不安感、認知機能障害など)を伴うため、著しく生活の質が低下するケースもあります。
線維筋痛症の認知度は低く、見た目では症状が伝わらないため、周りへの理解を得られず、そのことにより精神的な苦痛をうけることも少なくありません。
ここでは線維筋痛症について理解が深まるよう、病態や病院での治療方法などを解説しています。
パッと読みたい人は見出しをクリック
線維筋痛症の概念
線維筋痛症は、明確な器質的疾患(体の組織、細胞に変化がみられる疾患)を示さず、色々な症状がみられます。
線維筋痛症ガイドラインでは、以下のような定義が示されています。
線維筋痛症は身体の広範囲な部位に原因不明の慢性疼痛と全身性のこわばりを主徴候とし、随伴症状として多彩な身体、神経、精神症状を伴い、いずれの徴候も慢性疼痛と同様に身体診察や一般的画像検査を含む臨床検査で症状を説明できる異常を見出せないことにより、機能性身体症候群に属する特異なリウマチ性疾患
引用元:線維筋痛症ガイドライン2017
機能性身体症候群は、「明らかな器質的原因によって説明できない身体的訴えがあり、それを苦痛と感じて日常生活に支障をきたす病態」と定義され、主な病態は以下のとおりです。
- 過敏性腸症候群
- 顎関節症
- 舌痛症
- 慢性疲労症候群
- 間質性膀胱炎
線維筋痛症は、これらの機能性身体症候群を合併することも多くみられるとされています。
有病率
日本では、1.7~2.1%と報告され、女性に多くみられます。(とくに欧米諸国とほぼ同様の報告)
年齢では、中年に多くみられます。
小児にもみられる若年性線維筋痛症は、4.1%と報告されています。
若年性線維筋痛症は、共通の社会的心理背景があり非薬物療法が重要です。
症状
症状は広範囲にみられる慢性的な痛み(3ヶ月以上続く痛み)および、こわばりが主徴候です。
痛みの質は個人差もあり「締付けられる感覚」「ナイフで切られる感覚」など表現も色々です。
痛みは日によって違ったり、一日の中でも変動したり、さらには気候やストレス、睡眠不足などで症状が悪化します。
また、痛みやこわばりだけではなく、「神経症状」「精神症状」「身体症状」なども伴います。
〇主な神経症状
- 頭痛
- しびれ
- めまい
〇主な精神症状
- 睡眠障害
- 不安感
- 抑うつ
- 焦燥感
- 集中力の低下
主な身体症状
- 疲労感・倦怠感
- 腹部の症状
- 便通異常
疲労や倦怠感は、休養による回復困難であり、慢性疲労症候群と同様の症状がみられます。
診断基準
ここまで何度か書いてきたように検査では異常がみられないため、線維筋痛症は客観的な指標に基づく診断方法ありません。
ただし、膠原病やリウマチなど類似疾患と鑑別するために血液検査や画像検査などを行うことはあります。
現在の線筋痛症の診断は、線維筋痛症分類基準(1990)やACRの線維筋痛症予備診断基準(2010)を用いることが多いようです。
線維筋痛症分類基準は、からだの広範な部位にわたる疼痛が3カ月以上続き、指で4kgの圧力で触診を行い、 基準となる部位18カ所を押したうち11カ所以上が痛い場合は線維筋痛症と診断するものです。
しかし、線維筋痛症は痛みだけではなく精神症状も判断基準として重要となるため、線維筋痛症予備診断基準(2010)は、痛みがある部位の数と痛み以外の症状(疲労感、頭痛、腹痛など)の程度に合わせ重症度を出し、これを基に診断するというものです。
これらの診断基準も改訂されており2016年には、以下の項目が追記されています。
- 症状が少なくとも3か月間同様のレベルで現れる
- WPI≥7かつSSS≥5またはWPIが4〜6かつSSS≥9(WPIは痛みのポイント、SSSは身体症候および精神症状のポイント)
- 全身の痛みである(左右の上半身、左右の下半身、体軸部の5領域のうち4領域以上の痛み)
- 他の臨床的に重要な病気の存在が線維筋痛症の診断を除外しない
病院での治療方法
一般的な鎮痛薬は、効果がみられません。
また、線維筋痛症の治療方法は確立されておらず、個人にみられる症状(痛み、抑うつ、不眠など)に対処するために薬が処方されます。
線維筋痛症の一般的な処方薬は、プレバガリン、トラマドール、抗うつ薬(デュロキセチン、アミトリプチンなど)です。
薬物療法は生活の質を改善する効果もみられますが、痛みの強さの50%の減少は一般に10%から25%でしか達成されていないと報告されています。
非薬物治療
ヨーロッパの線維筋痛症のガイドラインでは、薬物療法は強く推奨されておらず、非薬物療法も組み合わせていくことも大切と考えらられています。
線維筋痛症に有効とされているのは運動であり、痛みや圧痛点および疲労の軽減がみられたという報告があります。
運動の内容は、「太極拳」「ヨガ」「ピラティス」「有酸素運動」「水中での運動」などです。
また、リハビリでも取り入れられるようなバランス運動、ストレッチ、筋力トレーニングなども効果がみられています。
精神症状もみられるため、認知行動療法(心理療法の1つ)の効果がみられたと報告されています。
他に効果的とされている療法は以下のとおりです。
- 鍼灸
- 徒手療法(マッサージ、オステオパシーなど)
- 理学療法(電気刺激、温熱療法など)
- プロバイオティクス
- 高圧酸素療法
- 感覚刺激(聴覚、視覚、振動覚など)
カイロプラクテイック心の考察
ここでは書いておりませんが、線維筋痛症は中枢神経系(脳)の異常が考えられてます。
また、線維筋痛症以外にも腰痛や首痛などの慢性的な症状は、脳が関わっていることが有力視されています。
そのため、脳に影響を及ぼす薬物療法や運動に効果がみられるケースが多いと考えられます。
個人的な見解ではありますが、太極拳のようなゆっくりとした動きは意識して行う必要があり、前頭前野と呼ばれる脳領域を活性化させやすいです。
前頭前野は、数ある脳領域の中枢として働き、機能低下は色々な問題(自律神経の乱れ、感情のコントロールが難しい、感覚過敏など)を引き起こします。
運動も慣れてくると無意識化でも体を動かせるようになり(他のことを考える、他の動作を同時に行うなど)前頭前野ではなく小脳の活動が重要となります。
例えば、歩くといった慣れた動きであれば、色々なことを考えたり、飲み物を飲んだり他のタスクもこなせます。
しかし、初めての動きであったり、可能な限りゆっくり動くことは意識して行う必要があり、前頭前野を活性化させることができ、結果として脳機能にポジティブな反応がみられるのではないでしょうか。
脳を健全に保つことも大事
カイロプラクテイック心は脳機能も評価し、神経可塑性を利用したアプローチも取り入れて、慢性的な症状、自律神経症状、発達障害のお悩みなどに対応しています。
線維筋痛症は、脳の影響も考えられるため、カイロプラクテイック心のアプローチが役に立てる可能性があります。
臨床的に線維筋痛症と診断された方、慢性的な症状に悩まれる方の対応もさせていただいております。
また、研究でも徒手的なアプローチは有効性がみられたという報告があることから、そのような面からも痛みの緩和できる可能性があります。
もちろん、カイロプラクテイック心のアプローチだけではなく、脳を健全に保つために運動、栄養、生活習慣も取り入れていただくことがベストです。
薬物療法以外にも何かよい療法がないかとお探しの方は、一度ご相談ください。
カイロプラクティック心線維筋痛症アプローチ
参考文献
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33114203/
線維筋痛症ガイドライン2017
投稿者プロフィール

- カイロプラクター
-
伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。
病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。
機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。
最新の投稿
 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング
栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群
脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告
部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告 栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ
栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

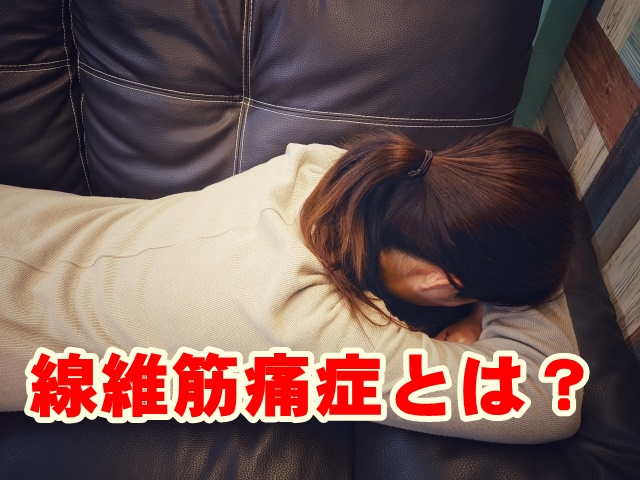





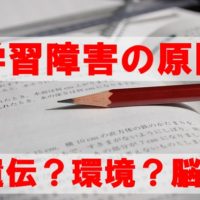

















この記事へのコメントはありません。