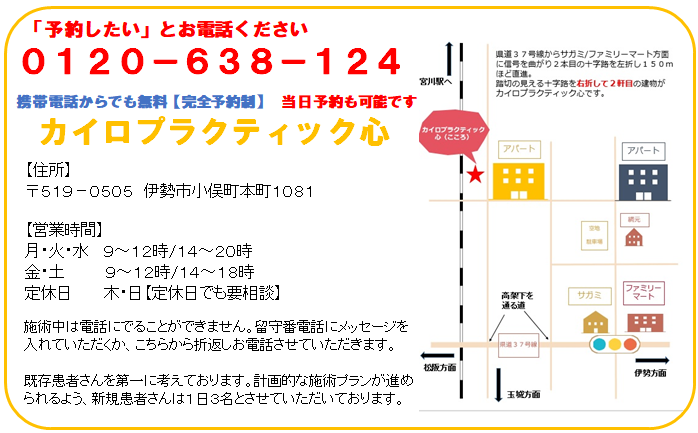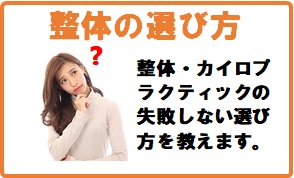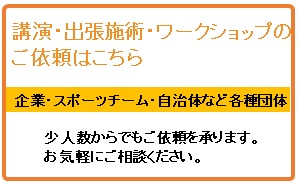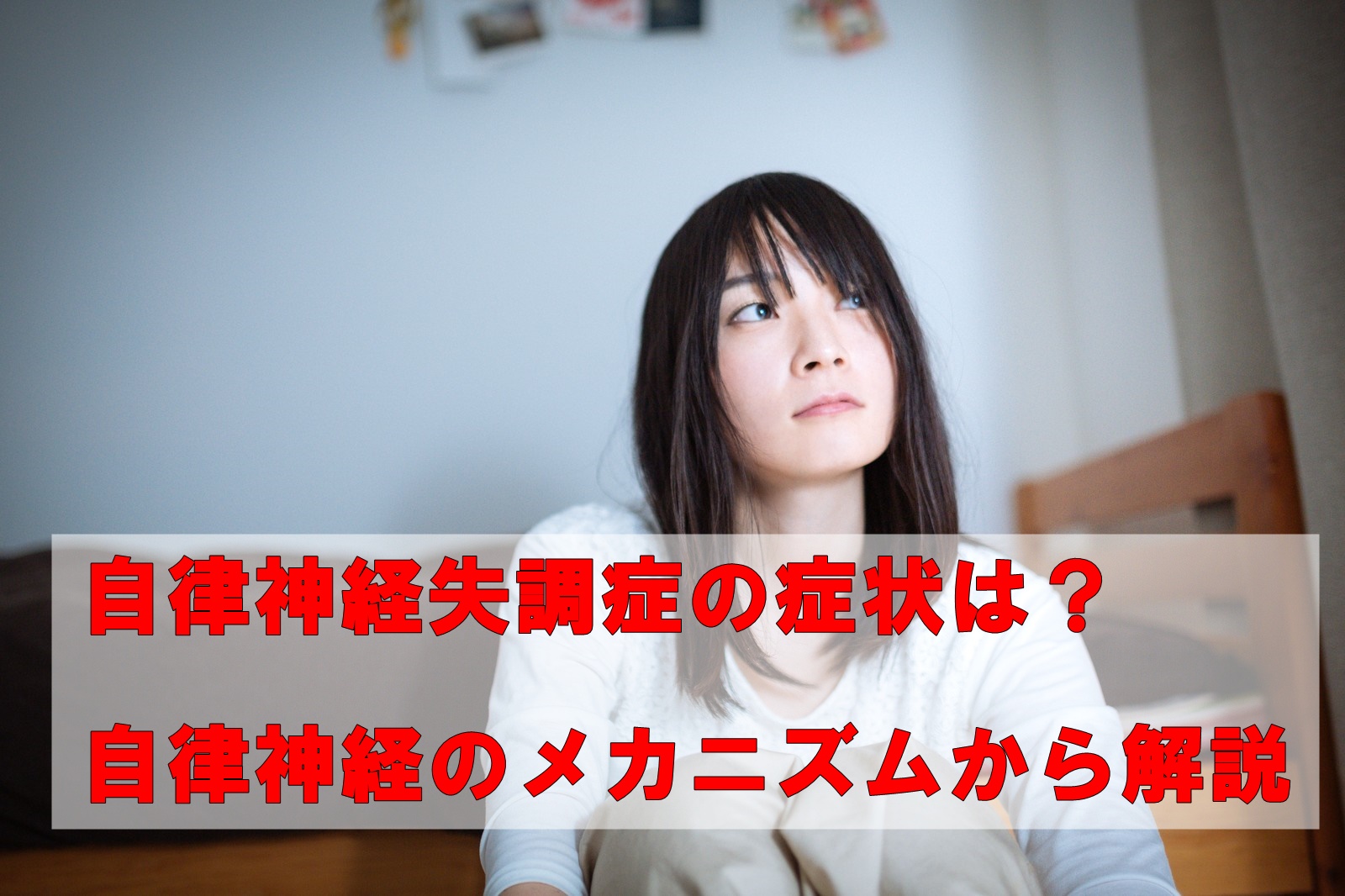
自律神経失調症は、自律神経が乱れていることが起因することで多くの症状がみられます。
そのため、同じ自律神経失調症と診断されている人でも現れる症状が違ったり、複数の症状がみられたりします。
ここでは自律神経の働きのメカニズムから、自律神経失調症の症状を解説していきます。
自律神経の身体に対する働き
自律神経は、身体の各器官を一定の状態(恒常性)を維持するために、交感神経と副交感神経の2つが以下のように働きます。
| 交感神経 | 身体の器官 | 副交感神経 |
|---|---|---|
| 散大 | 瞳孔 | 縮小 |
| 分泌抑制 | 涙腺 | 分泌促進 |
| 心拍と血液の排出量の増加 | 心臓 | 心拍と血液の排出量の低下 |
| 収縮 | 血管 | 拡張 |
| 拡張 | 冠状動脈 | 収縮 |
| 弛緩 | 気管支 | 収縮 |
| 消化が抑制 | 胃 | 消化の促進 |
| グリコーゲンを分解し糖を血液に放出 | 肝臓 | グリコーゲンを合成 |
| 消化の抑制 | 小腸・大腸 | 消化の促進 |
| インスリンの分泌減少 | 膵臓 | インスリンの分泌増加 |
| 弛緩 | 胆嚢 | 収縮 |
| 分泌促進 | 副腎 | 作用無し |
| 排尿の抑制 | 膀胱 | 排尿の促進 |
| 分泌促進 | 汗腺 | 作用無し |
| 収縮 | 立毛筋 | 作用無し |
この表を見てわかるように自律神経は全身の調整を行っており、上手く働かなければ全身に何らかの症状が現れてもおかしくありません。
自律神経と脳の関係性
自律神経は、脳を介さない反射の作用もありますが、脳(脳幹、小脳、視床下部、大脳辺縁系、大脳皮質など)でもコントロールされ適切に調整されています。
脳幹
脳幹は生命維持に必要な機能を無意識化でコントロールしている中枢であり、自律神経を介して以下のような働きを担っています。
- 血液循環
- 呼吸
- 嘔吐
- 嚥下(飲み込むときの運動)
- 排尿
視床下部
自律神経の重要な中枢として働いています。
また、大脳辺縁系と密接に関与し、情動や本能的な行動をコントロールしている領域です。
- ホルモンの分泌調整
- 摂食行動、飲水行動、性行動などの本能的な行動や情動(怒り、不安など)行動の統合
- 体温調整
- 血糖調整
- 日内周期調整(体内時計)
- 水分調整
大脳皮質
島と内側前頭前野、大脳辺縁系の領域が関わっています。
- 島⇒内臓感覚
- 内側前頭前野⇒自律神経の抑制
- 大脳辺縁系⇒情動による自律神経への促通
大脳辺縁系は視床下部と密接な関係性があり情動(快楽、報酬、不安、恐怖など)に伴う自律神経反応をコントロールしています。
例えば、恐怖や不安を感じてその場から走って逃げる、応戦しようとする場合は交感神経を働かせ筋肉が活動しやすくなります。
自律神経失調症は、脳と自律神経の関りにより精神的な症状も現れます。また、身体の各器官だけでは説明できない症状も脳が影響しているといえます。
自律神経失調症の症状
自律神経の働きと自律神経失調症でみられる症状の関連は以下のとおりです。
- 動悸⇒交感神経が優位に働くことによる心拍の増加。
- 喉が渇く⇒交感神経が優位に働くと唾液も抑制される。
- 目の乾き、まぶしい、目の疲れ⇒交感神経が優位になると瞳孔が大きくなりまぶしさを感じ、瞳孔を大きくする筋肉が疲労し疲れを感じます。そして、涙腺の分泌も減少するため目が乾く。
- 汗をかく⇒交感神経優位により汗腺の分泌が促進。
- 胃腸障害(下痢、便秘、胃の不快感、吐き気など)⇒交感神経優位により胃腸の動きが抑制され、食事中の分泌量もコントロールできなくなると胃酸過多による胃痛、不快感などもみられる
- 排尿障害(排尿が困難、残尿感、頻尿など)⇒膀胱の収縮がコントロールできない
ここに書いた症状以外にも、自律神経を介した症状は多くみられます。
発熱(微熱)
体温調整は、視床下部にある体温調整中枢による働きです。
暑くなれば、末端の毛細血管を拡張させ熱を放出しやすく、さらに汗によっても熱を放出できます。
寒いときは熱を逃がさないために末端の毛細血管を収縮させ、熱を運ぶ血液が流れないようにします。
このように血管の収縮、拡張で体温をコントロールしている側面があり、自律神経が乱れ交感神経が常に優位に働いていると血管の調整が上手く機能せず熱を放出しにくい状態となります。
そのため、発熱しやすく汗が出にくい人であればより顕著に現れやすいです。
ある程度は体温調整中枢で調整されますが、自律神経の乱れによりほてり、微熱、暑く感じる、寒く感じるなどの症状があらわれやすくなります。
※汗腺は環境にも左右され、運動をしない、涼しい所に年中いるなど汗をかかない環境にいると汗腺が閉じてしまい交感神経が優位でも汗はかきにくいです。
しびれ、痛み
しびれ、痛みのメカニズムは複雑ですが、交感神経と関わるC線維が自律神経失調症の痛みやしびれに影響していると考えられます。
1つの作用としては、通常はC線維はAβ線維(触覚)に抑制されていますが、Aβ線維の虚血によりC線維が抑制できなくなるとしびれ感につながるときがあります(血管収縮により皮膚表面までの血液循環が悪化するため)
また、交感神経が優位に働くことによりC線維への刺激が入りやすく、普段なら気にならない刺激(少しストレッチされる、少しの炎症など)でみ痛みやしびれとして脳が認識してしまう可能性があります。
息苦しい
交感神経が優位であると酸素を多く取り込むシステムとなりますが、血中の二酸化炭素の量も重要で酸素の比率が多くなりすぎても、身体中に酸素を運ぶことができません。
そして、さらに呼吸をしようとしても限界があり、息苦しさを感じることがあります。
また、身体中に酸素を運べていないため、だるさや疲れやすさを感じるケースもあります。
精神症状(不安感、イライラ、情緒不安定、不眠など)
情動行動に関係する視床下部の誘因は体内のグルコース・インスリン、イオン濃度などの内部情報を統合により形成されるそうです。
自律神経の乱れにより、肝臓、すい臓のグルコース、インスリンの分泌量の異常が、精神的な症状を併発するとも考えられます。
ただ、自律神経失調症になりやすい人は、「真面目」「几帳面」「努力家」など不安になりやすい性格の持ち主であることが多く、精神状態の悪化が起因していることも少なくありません。
男性は勃起障害、射精障害
勃起するには副交感神経が優位に働く必要があり、交感神経が活性化していると勃起障害になります。
また、自律神経の乱れにより交感神経にうまく切り替えられないと射精ができません。
「自律神経失調症の症状?」と思ったあなたへ
自律神経は、身体を自動的に調整する機能をもつため、不調になると身体のあらゆるところに症状が現れる可能性があります。
ネットやテレビなどで色々な情報が入手できる昨今では、自己判断で自律神経失調症と考えてしまう人も少なくありません。
しかし、その症状のなかには重大な病気(脳疾患、内分泌系の疾患など)が隠されている可能性もあるため、自己判断ではなく病院でしっかりと診断してもらいましょう。
「病院へ行っても異常が見当たらない」「自律神経失調症と診断され薬物療法にも効果が無い」など病院でも改善されない不調は、中枢神経(脳)を含めた身体の機能が低下しているかもしれません。
カイロプラクティック心は、脳を含めた神経系も評価し、身体の機能を向上させる施術を行います。
一人で悩まず、ぜひご相談ください。